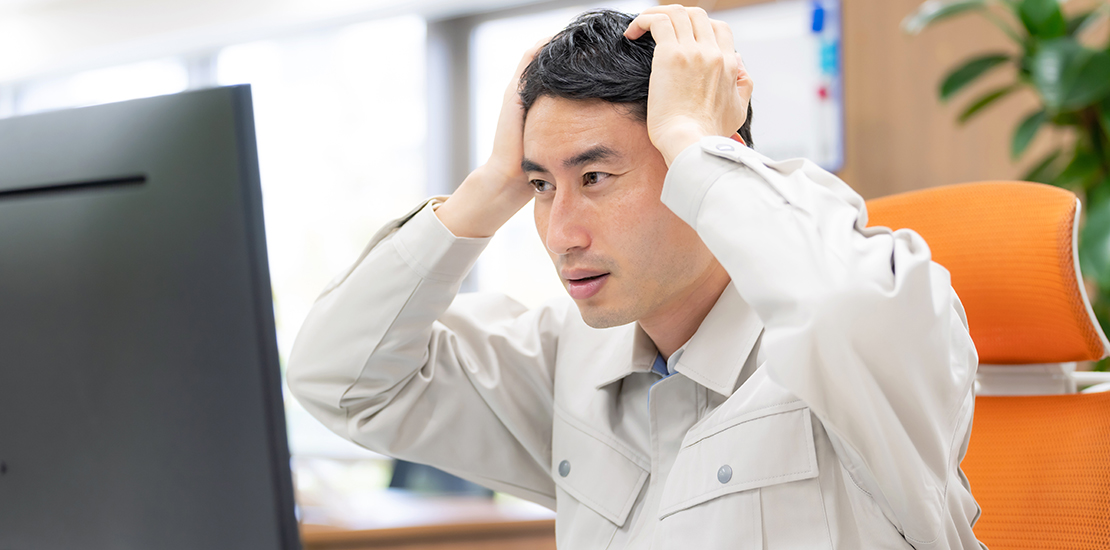日本のビジネスにおいて、業種を問わず人手不足が深刻化しています。
消費者に住まいやオフィスを提供する不動産業界でも、人手不足が起きているのか疑問に感じる人は多いでしょう。
本記事では、不動産業界における人手不足の実態についてお伝えします。
人手不足の解決策として注目されている「M&A」についても紹介するため、人手不足に悩む不動産経営者はぜひ参考にしてください。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
不動産業界における人手不足の実態
不動産業界では、正社員・パートタイムともに人手不足が続いています。
厚生労働省が公開している「労働経済動向調査(令和3年8月)の概況」によると、不動産業界における正社員の労働者過不足判断 D.I.は約20~30ポイントと、高い数値を示しています。
また、正社員ほどではないものの、パートタイムの労働者過不足判断 D.I.も令和3年時点では常に不足超過(足りていない)となっています。
労働者過不足判断 D.I.とは、人材不足の事業所から人材過剰な事業所を差し引いた数値で、このD.Iが高いほど労働者が不足している事業所であると判断されます。
そのため、不動産業界において、正社員の数は不足している傾向が強いといえます。
不動産業界で人手不足が起こっている原因
なぜ、不動産業界で人手不足が起こっているのでしょうか。それには、主に2つの原因が考えられます。
入職者の少なさ
不動産業界の人手不足は、入職者の少なさによるところが大きいでしょう。
厚生労働省の「令和4年上半期雇用動向調査結果の概況」によると、不動産業界の入職者は2022年の上半期だけで約9万人です。
一方で、全業種合計の入職者は約475万人もいます。不動産業界の入職者は、全体の2%程度にしか満たないのが現実です。
入職者が少なければ、現状の人材だけで業務を回すことになります。仕事の需要が高まれば、現状の人材ではカバーしきれなくなり、人手不足に陥るでしょう。
不動産業界における離職者の多さも、人手不足を引き起こす一因です。不動産業界では、長時間残業といった労働上の問題も散見されるため、離職率が高い傾向にあります。
厚生労働省にて公開されている「令和4年上半期雇用動向調査結果の概要」では、入職者と同様に離職者のデータも公表されています。
同調査によると、不動産業界の離職者は約6.6万人もいるようです。約9万人の入職者に対して約6.6万人の離職者は、決して少なくありません。
また「不動産業ビジョン2030」によると、不動産業界に携わる人材の約50%が60歳以上と、高齢化が進んでいるのが現状です。
既存人材の高齢化が進んでリタイアが増えれば、今後はさらに人手不足が加速する懸念もあります。
競合の増加による人材の分散
競合の増加によって、不動産業界の人材が分散していることも考えられます。
「不動産業ビジョン2030」によると、不動産業界の法人数は右肩上がりで増えているようです。
不動産業界は他業界と比べると、低額な資金で開業できます。また、不動産情報の共有システム「レインズ」により、新規参入者でも容易に不動産情報にアクセス可能です。
こうした理由から、不動産業界は新規参入のハードルが低いため、昨今ではコンビニエンスストアよりも多く存在します。
一方で、すでにご紹介したように入職者はそれほど多くありません。限られた人材を多くの不動産会社で奪い合う構図になれば、1社あたりに確保できる人材は少なくなるでしょう。
このような人材不足の状況において、有効な打ち手となるのが外部人材の活用です。
不動産業界の人手不足を解消するための対策・戦略
不動産業界の人手不足を解消するための対策・戦略について解説します。
IT化の推進による生産性向上
不動産業界全体の入職者数には限界があり、不動産会社が増やせるものではありません。
取り込める人材には限りがあるため、自社の既存人材だけで業務を回すための工夫が必要でしょう。
例えば、Web予約システムを導入することで、電話や窓口対応に生じる負担を軽減可能です。また「RPA」を導入すれば、日常的な繰り返しの業務を自動化できます。
昨今では「オンライン内見」が行えるサービスもあり、内見のテレワーク対応も可能です。
このように、IT化の取り組みにより生産性を向上することで既存人材でも業務を回しやすくなるでしょう。
また、IT化による業務効率化とあわせて、社員のスキル向上も欠かせません。
アウトソーシングの活用
自社の手に余る業務があれば、アウトソーシング(外部委託)を活用することもおすすめです。
例えば、事務作業をフリーランスの作業者に委託することで、自社スタッフはコアな業務に集中できます。
クラウドソーシングサイトを利用すれば、容易にアウトソーシングが可能になるでしょう。
依頼することに費用はかかるものの、交渉次第ではコストを抑えられます。
労働条件・労働環境の見直し
労働上の問題が多いとスタッフの離職を引き起こしやすくなるため、労働条件や労働環境に問題があれば見直しましょう。
スタッフが納得できる給与体系や福利厚生であれば、既存スタッフの離職は抑制できるでしょう。
また、求人を見た求職者からの印象もよくなるため、応募者の増加も期待できます。
M&Aの実施
不動産業界でも増えている「M&A」を実施することも検討しましょう。
不動産業界にとってM&Aを実施するメリットは多く、さまざまな課題の解決につながります。
ただし、M&Aは戦略や相手企業の選び方によって、得られる成果が大きく異なります。
そのため、M&Aを成功させるうえでは、豊富な実績を持つ専門家へのサポート依頼をおすすめします。
不動産業界の課題解決につながったM&Aの事例3選
不動産会社がM&Aを実施することで、人手不足以外にもさまざまな課題を解決できます。
しかし、M&Aの具体的なイメージが湧かない人も多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産業界の課題解決につながったM&A事例を3つ紹介します。
A社とB社のM&A(株式譲渡)
A社は、仲介・管理を専門とする不動産会社です。A社は地域に根差した事業を続けてきたものの、人材確保や資金力の面で課題を感じていました。
そこで、M&Aの「株式譲渡」によって経営権を譲渡し、東証マザーズ上場企業であるB社の傘下に入っています。
B社は、約100億円もの売上高を持つ大規模な不動産会社であり、高い資金力・ブランド力を持っています。
M&Aを行うことによって、B社のブランド力を取り込めたため、応募者が大幅に増えて、A社は人材確保の課題解決を実現しました。
C社とD社のM&A(吸収合併)
C社は、駐車場のコンサルティング事業を展開する不動産会社です。C社には、子会社として不動産の売買・管理を専門とするD社の存在がありました。
ただし、両社の関係性は株式によるものであり、D社の法人格はC社とは異なります。
C社は、組織の合理化を図るために、M&Aの「吸収合併」によりD社を自社に統合しました。
吸収合併によってD社の法人格は消滅し、D社の権利や義務はすべてC社に集約されています。
これによって、各種管理の効率化や連携の強化が期待されます。
E社とF社のM&A(株式交換)
E社は、不動産のマッチングサービスを提供する企業です。当時は不動産市場が落ち込んでいたこともあり、さらなるサービス品質向上を課題としていました。
そこでE社はM&Aの「株式交換」によって、海外で富裕層向け不動産の販売代理事業を展開するF社を完全子会社化しています。
現地でも高い評価を受けているF社の人材や、ノウハウを取り込むことで、よりサービス品質向上につなげる狙いがあります。
このM&Aは、E社が中長期的な成長戦略を実現するための大きな一歩となりました。
まとめ
多くの不動産会社では、正社員・パートタイムともに人手不足が常態化しています。
不動産業界で人手不足が続いている理由として、入職者の低さや離職率の高さ、人材の分散などが挙げられるでしょう。
不動産業界が人手不足を解消するうえでは、IT化の推進による生産性向上、アウトソーシングの活用などが求められます。また、人手不足や後継者問題を解決するうえでは「M&A」も有力な選択肢です。
ただし、M&Aには高度な専門知識が要求されるため、未経験の経営者が適切に進めることは難しいでしょう。不動産会社がM&Aにより課題解決を図るのであれば、専門家に相談するのをおすすめします。
M&Aを上手く進められるかご不安な場合は、不動産業界におけるM&Aのサポート実績が豊富な「M&Aベストパートナーズ」へお気軽にご相談ください。