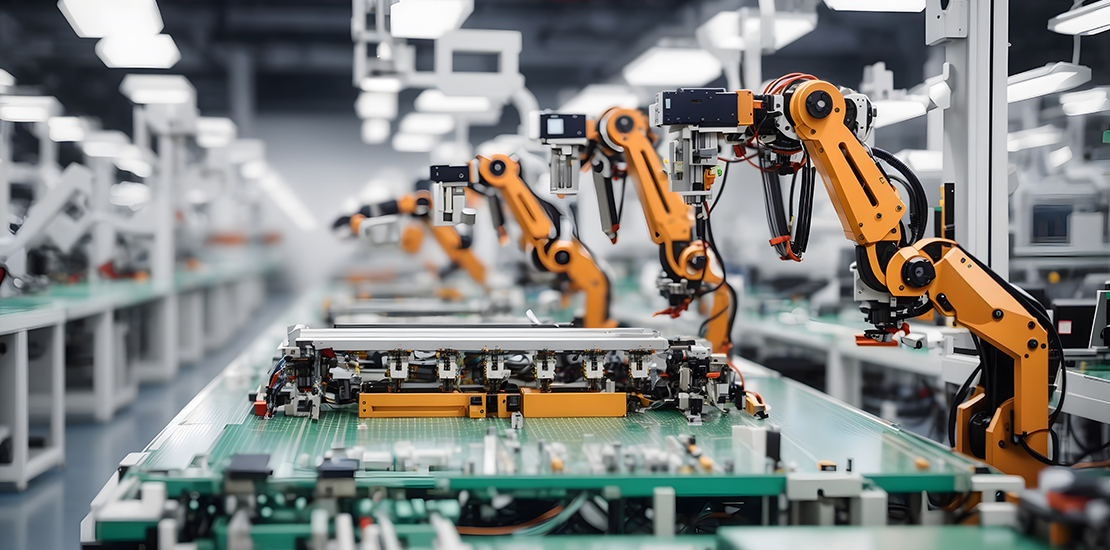近年、調剤薬局の業界はますます厳しい経営環境に直面しています。
医療費削減の圧力・薬価改定による収益減少・インターネット薬局の台頭など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、経営者たちは生き残りのための新たな戦略を模索し続けなければなりません。
また、地域密着型の薬局にとっては、人口減少や高齢化といった社会的変化への対応も必要です。
本記事では、調剤薬局経営が直面する厳しい現状と抱えている課題、今後の生き残りをかけた戦略について詳しく解説します。
経営に悩みを抱える調剤薬局の経営者の方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
調剤薬局の経営は厳しい?
薬価の改定や医療費の削減など、近年では調剤薬局の経営は厳しい環境に置かれています。
高齢者の数が増加し、薬に対するニーズは尽きません。しかし、ジェネリック医薬品の推奨による収益の減少、インターネット薬局や大手ドラッグストアチェーンの台頭が原因で経営に支障をきたす調剤薬局は少なくありません。
また、薬剤師や事務職などの人材不足も、経営を厳しくしている原因です。
調剤薬局業界が抱える課題
調剤薬局の業界は高齢化が進むにつれて需要は拡大すると思われがちですが、実際にはさまざまな課題を抱えています。
調剤薬局が抱える課題は、次の2つです。
それぞれ詳しく解説します。
利益の減少
調剤薬局業界が抱える課題として、国による医療費削減の取り組みにより、調剤報酬や薬価の引き下げで利益が減少していることが挙げられます。
高齢化社会によって医療費は年々増加しており、国は医療費を削減するためにさまざまな施策を行っています。ジェネリック医薬品の推奨もその一つです。
なかでも、複数の店舗を持っている大手調剤薬局や医療機関の近くで開業している門前薬局は、この取り組みによる影響は大きいです。
利益率の低下は、来店者が増えても改善することは難しく、解決が難しい問題といえます。
慢性的な薬剤師不足
慢性的な薬剤師不足も、調剤薬局の経営が難しいといわれる原因です。薬剤師不足が生じる理由として、インターネット薬局や大手ドラッグストアの増加が挙げられます。
薬剤師自体の数は増加傾向にあるものの、調剤薬局一軒あたりの薬剤師が不足し、店舗数の拡大や事業継続の妨げとなっています。
調剤薬局業界の展望
収益の減少や人手不足が課題の調剤薬局の現状と、将来の展望を解説します。
調剤薬局の市場動向
厚生労働省の発表によると、2023年度の調剤医療費(電産処理分)は約8兆3,077億円で、前年と比べて5.4%増加しています。また、処方箋発行枚数も前年比+6.1%となっています。
一方で、処方箋一枚あたりの調剤医療費は前年比-0.5%と減少しており、調剤報酬や薬価の引き下げの影響が顕著に現れています。
そのほかに、大手ドラッグストアが調剤部門を設けるようになったり、インターネットによる処方箋の対応が可能にもなっています。
安定したニーズは見込めるものの、実店舗だけでなくインターネットでの対応が可能なため、調剤薬局の市場は飽和状態にあるといえるでしょう。
参考サイト:調剤医療費(電算処理分)の動向~令和5年度版~
調剤薬局の将来性は?
既に飽和状態となっている調剤薬局の業界は、今後さらに少子高齢化が進むことで医療費削減の圧力が強まり、経営環境は厳しくなるでしょう。
具体的には、DX化をすることで業務効率が期待できますが、そのためには設備投資が必要です。収益の減少が進む調剤薬局では資金調達が難しく、資産規模に余裕のある大企業による寡占化が進む可能性があります。
調剤薬局経営は儲かる?
飽和状態となり、収益が下がってきている調剤薬局は、経営を続ける子で設けることができるのでしょうか。
調剤薬局を経営することで得られる年収の目安と、収益を増やすための経営戦略の具体例をご紹介します。
調剤薬局経営の年収について
新たに調剤薬局を開業した場合、初年度の年収は400万円を下回る可能性があります。一方で、地域に根付き、ある程度名の知れた小規模の調剤薬局の場合は、800万円弱が目安となります。
大手チェーン薬局のフランチャイズオーナーとなった場合は、700万円前後の年収が得られることもあるでしょう。
このように、調剤薬局の経営者が得る年収は、薬局の規模や経営状況によって大きく異なります。
薬局の規模が大きいほど年収が安定する可能性は高くなりますが、小規模でも地域密着型で安定した集客が見込める場合、大手チェーンの薬局より儲かるケースもあります。
調剤薬局の収益を左右する「処方箋枚数」
調剤薬局の収益は、処方箋を取り扱うことで発生する調剤報酬から得られます。調剤報酬には、基本料金や薬剤費、指導料などが含まれます。
薬局が受け取る収益は、処方箋枚数に影響されます。取り扱う処方箋の枚数が多ければ、調剤報酬もそれに応じて増えます。
処方箋枚数を自発的に増やすことは、とても難しいです。そのため、オンラインによる処方箋の取り扱いなど別の収益モデルを検討したり、DX化などで作業効率を向上させたりするなど、新たなビジネスモデルの検討が必要です。
調剤薬局経営の生き残り戦略
調剤薬局の収益は、法によって定められています。そのため、勝手に値上げをして収益を増やすことはできません。
では、調剤薬局として市場で生き残るためには、どのような方法があるのでしょうか。調剤薬局として生き残るための経営戦略をご紹介します。
デジタル化とITの活用
電子薬歴システムを導入することで、薬剤師が患者の情報を効率的に管理し、迅速な対応が可能になります。
また、オンライン予約システムによって患者様が事前に予約することで、待ち時間を減少させることができます。
業務のデジタル化やシステムの導入によってサービスの質が向上し、患者様の満足度や信頼度の引き上げにつながるでしょう。
サービスの多様化
調剤薬局の本来の業務である薬の販売だけでなく、定期的な健康チェックや栄養相談など、地域の健康増進に寄与することも経営戦略の一つです。
また、高齢者が増えている地域の場合、在宅での薬剤管理や訪問サービスの提供も喜ばれるでしょう。
こうしたサービスは、訪問診療や在宅医療のニーズとも密接に関連しており、患者の生活の質(QOL)を向上させる手助けとなります。
また、サービスを通して地域に根付き、認知度の向上にもつなげられるでしょう。
他業種とのコラボレーション
地域の医療機関や介護施設と連携し、医療情報を共有すれば、垣根を超えたサービスが提供できるようになるでしょう。
例えば、健康食品を販売している店舗やフィットネス施設といった他業種と提携することで、総合的な健康サポートをすることができます。
質の良いサービスが提供できれば、ユーザーや協業企業によるクチコミが広がり、認知度拡大につながるでしょう。
地域密着型のマーケティング
実店舗を持っている調剤薬局の場合、地域密着型のマーケティングを行い、近隣住民へのアプローチが重要です。
主流となっているSNSやWebサイトを活用した、広範囲に向けたアプローチも大切です。その他に、地域のイベントに積極的に参加したり地域誌に広告を出したりするなど、地域に密着した運営も大切です。
M&Aという選択肢
近年では、調剤薬局業界でもM&A(企業の合併・買収)が活発に行われています。
M&Aにはさまざまな方法があります。経営基盤の安定した企業の傘下へ入ることで、事業を継続させていくことができます。
また、後継者不足に悩みがある場合、事業を引き継ぐこともできるでしょう。
自力での立て直しが難しいと感じたときは、M&Aという選択もおすすめです。
調剤薬局業界におけるM&Aの動向
事業を継続するための選択肢の一つであるM&Aは、調剤薬局業界ではどのようにカツオ湯されているのでしょうか。
調剤薬局業界におけるM&Aの動向について、詳しく解説します。
調剤報酬や薬価の引き下げに対応するためのM&Aが増えている
調剤報酬や薬価の引き下げは、複数店舗を持つ大手調剤薬局に大きな影響を与えています。
このような状況を受け、大手調剤薬局ではM&Aにより事業を拡大し、収益や販売網を広げる動きが活発化しています。
また、経営難に陥った小規模の調剤薬局が、M&Aにより大手調剤薬局の傘下に入ろうとする動きもよくみられます。
かかりつけ薬局に移行するためのM&Aが増えている
近年では、かかりつけ薬局に移行するためにM&Aを実施するケースも増えています。
厚生労働省は、地域の医療を強化するため、かかりつけ薬局への移行を推進しています。そのために、「2025年には全ての調剤薬局をかかりつけ薬局に移行する」という方針を打ち出しました。
かかりつけ薬局に移行するためには、ICTの導入※や24時間体制で対応するための薬剤師の確保など、多くの準備とコストが必要です。
資金難によって準備が難しい調剤薬局も多く、M&Aによって準備資金や新たな薬剤師の確保をしようとするケースが増えています。
※オンラインによる資格の確認や電子処方箋、電子お薬手帳などの通信技術
後継者不足を解消するためのM&Aが増えている
後継者不足を解消するためにM&Aを実施する調剤薬局も増えています。
後継者不足はさまざまな業種で深刻な問題となっており、調剤薬局業界でも同様です。特に中小規模の調剤薬局では後継者不足の問題を解消できず、廃業となるケースもあります。
また、厚生労働省が2020年に調査した「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 」の結果では、薬局の開設者もしくは法人の代表者の最も多い年齢は60〜69歳でした。全体に占める割合は59.9%と、半数以上が高齢という結果になっています。
この結果から、後継者不足の課題は今後も続くと予測でき、M&Aによって第三者に事業承継をする企業は増えると考えられます。
調剤薬局業界におけるM&Aのメリット
調剤薬局業界におけるM&Aでどのようなメリットがあるのか、イメージが湧かないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
調剤薬局におけるM&Aのメリットについて、売り手側・買い手側に分けて解説します。
売り手側のメリット
売り手側となる調剤薬局のメリットとして、次のようなことが挙げられます。
- 後継者不足の解消による薬局の存続
- 安定した経営
- 創業者利益を得られる
後継者がいないために薬局の継続を悩んでいる場合、M&Aによって事業を承継し、薬局の存続ができることは大きなメリットです。
また、薬局の存続は、勤めている従業員の雇用維持にもつながります。
資金力のある大手調剤薬局とM&Aを実施した場合、その資金力を活用して経営が立て直せる可能性もあるでしょう。資金だけでなく、薬剤師の補充や設備の導入など、さまざまなメリットが得られます。
事業の売却をすることで創業者利益を得られることも、M&Aのメリットです。調剤薬局は需要が高く、条件によっては高額で売却できる可能性があります。
買い手側のメリット
調剤薬局業界におけるM&Aでは、買い手側にも多くのメリットがあります。
- 人材の確保
- 事業規模の拡大
- 仕入れ額を抑えられる
M&Aは、売り手側の人材をそのまま引き継ぐケースが多いです。慢性的な人手不足が問題となっている調剤薬局業界において、優秀な人材の確保は大きなメリットといえるでしょう。
また、かかりつけ薬局に移行するためには、薬剤師の確保は欠かせません。M&Aにより薬剤師を増やすことができれば、かかりつけ薬局への移行もスムーズに行えるでしょう。
また、事業規模が拡大できることもM&Aのメリットです。調剤薬局業界は調剤報酬や薬価の引き下げによって収益が減少傾向にあります。しかし、M&Aをすることでスムーズに事業規模の拡大できる可能性があります。
事業規模の拡大は、製薬会社や卸売業者からの仕入れコストを抑えられる可能性も期待できます。1度でで多くの医薬品を仕入れることで、輸送にかかる費用を抑えられるでしょう。
調剤薬局業界におけるM&Aのリスク
調剤薬局業界におけるM&Aは、多くのメリットが得られる一方でリスクも存在します。
調剤薬局業界におけるM&Aのリスクについて、買い手側・売り手側に分けて解説します。
買い手側のリスク
調剤薬局業界におけるM&Aの買い手側のリスクには、以下のようなことが挙げられます。
- 薬剤師が離職する可能性がある
- 買い手側・売り手側の従業員同士が反発する可能性がある
- 簿外債務が発生する可能性がある
M&Aの成立後は、経営方針やシステムの統合など、PMIと呼ばれる統合のプロセスが必要です。PMIでは、最小限のリスクで最大限の効果を導き出すために、新たな経営方針や組織体制の構築が不可欠です。
しかし、統合がうまくいかなかった場合は従業員同士に摩擦が生じ、離職につながるリスクがあります。
M&A成立までの調査に漏れがあった場合、成立後に売り手側の債務が発覚し、余計な負債を背負う可能性も否定できません。
M&Aによって買収や合併をする場合、入念な調査と統合後の適切なプロセスが必要です。
売り手側のリスク
調剤薬局業界におけるM&Aの売り手側のリスクには、以下のようなことが挙げられます。
- 従業員の人員整理が実施される可能性がある
- 顧客や取引先、従業員との関係性が悪化する可能性がある
相手企業の選定に失敗したとき、このようなリスクが生じやすいです。リスクを回避するために、相手企業の選定は慎重に行うことが重要です。しかし、自社のみで希望にあう相手企業を見つけるのは難しいでしょう。
そのため、M&Aを実施する場合は検討段階でM&Aの専門家に相談することが大切です。M&Aの専門家に依頼すれば、独自のネットワークから自社の希望に合う相手企業を紹介してくれます。
調剤薬局業界におけるM&Aの成功事例
M&Aベストパートナーが担当した、調剤薬局業界におけるM&Aの成功事例をご紹介します。
大手に傘下入りによる安定的な経営を実現するためのM&A
有限会社アトムメディカル様は、2001年に神奈川県鎌倉市に調剤薬局を開業しました。さらに、JR「大船駅」「北鎌倉駅」のそれぞれの駅前で、2つの店舗を運営しています。有限会社アトムメディカル様の調剤薬局は、家族経営しており、従業員も10名足らずでした。
M&Aを検討するようになる背景には、厚生労働省が推進しているかかりつけ薬局への移行がありました。かかりつけ薬局では24時間営業が求められ、家族経営の調剤薬局では生き残りが厳しいと考えM&Aの実施を考えます。さらに、ジェネリック医薬品の普及による収益の減少や、薬剤師の人材確保が難しくなったことなども要因です。
その後、店舗数が100店舗以上あり、売り上げ規模が200億を誇る株式会社エスシーグループ様とのM&Aを行うことになります。
事業の継続・従業員の継続雇用を実現するためのM&A
株式会社ファルマシア様の古林氏は、49歳のときに宮崎県で調剤薬局の経営をしていました。その後、福岡県久留米市にある病院の院長から「調剤薬局を開業してほしい」との強い要望を受け、福岡県久留米市でも調剤薬局を始めます。
宮崎県と福岡県久留米市で2つの調剤薬局を経営していた古林氏は、体調に不安をかかえ、67歳のときに宮崎県の調剤薬局をM&Aにより手放しました。しかし、70歳を目前に福岡県久留米市の調剤薬局もM&Aにより事業承継しようと検討し始めました。
古川氏は、これまで通り病院とのよい関係を保て、従業員の雇用を守れる相手企業を条件として提示し、同じ地域で複数の調剤薬局を経営している会社を紹介されます。
その後、株式会社ファルマシア様は、M&Aにより事業承継を実現しました。
従業員の雇用維持と相手企業との相性・将来の展望をマッチさせたM&A
株式会社松栄堂薬局様は、愛知県内で調剤薬局を営んでいる企業です。
一般的な調剤薬局と異なるのは、在宅医療に特化し患者の自宅や介護施設へ、処方薬を配達しているという点です。
しかし、もともと少人数の従業員で事業を展開していたため、人手不足が深刻化していました。
そのため、このようなビジネスモデルは、やがて限界を迎えるのではないかといった不安があったといいます。
少しずつM&Aという選択肢が頭をよぎるようになり、M&A支援会社の担当者と面談をすることになりました。
M&Aにあたって特に重視したのは「自社へのメリットや従業員の待遇」そして「譲受企業との相性や将来の展望」の2点でした。
M&A支援会社からは、北海道を拠点に医療・ヘルスケア事業を幅広く手掛ける株式会社ミライシアホールディングが紹介され、経営トップ同士の面談が行われました。
ミライシアホールディングにとっては、東海地方への初進出となることから期待が大きかったです。
さらに、M&Aにあたって懸念していた従業員の待遇に関しても問題がクリアになり、M&Aの決断に至りました。
ミライシアホールディングの傘下に入るまでは資金的な余裕もなく、新たな事業に挑戦することも難しい状況でした。
しかし、現在ではさらなる成長に向けて、チャレンジングな経営ができるようになったといいます。
まとめ
調剤薬局業界では、厚生労働省によるかかりつけ薬局の推進や調剤報酬・薬価の引き下げなどに対応するため、M&Aを実施する企業が増えています。
また、中小規模の調剤薬局では、後継者不足を解消するためのM&Aも活発になっています。
調剤薬局業界におけるM&Aでは、薬剤師の確保や事業の拡大など、さまざまなメリットが得ることが可能です。一方で、把握しておくべきリスクも存在します。
M&Aをすることで生じるリスクを最小限に抑えるためには、M&Aの専門家への依頼がおすすめです。
「M&Aベストパートナーズ」では、調剤薬局業界におけるM&Aの実績を数多く持っております。調剤薬局業界におけるM&Aを検討している方は、ぜひM&Aベストパートナーズにご相談ください。