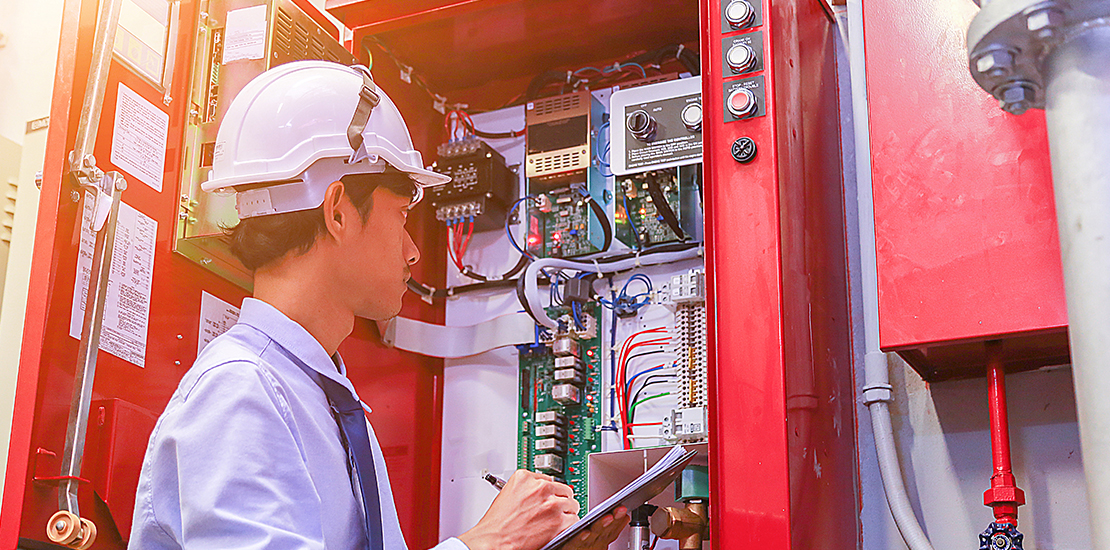2024年から始まった時間外労働の規制強化、さらに多くの物流会社が課題を抱える2025年問題などの影響から深刻化する物流クライシス。
「2024年、2025年問題というけど、いつ収束するのだろう」と不安を抱える経営者の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、物流クライシスが起きている原因、そして業界へ与える影響について詳しく解説します。
あわせて、物流クライシスを乗り越えて生き残る方法もご紹介するので、生き残りをかけた課題解決の方法を模索している方はぜひ参考にしてください。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
物流クライシスの原因
物流クライシスが起きた原因として、以下のことが挙げられます。
EC市場の急激な拡大
1990年代後半、インターネットの普及とともに本格的に始まったEC市場は、2000年代後半にスマートフォンの普及や高速回線の整備によって加速しました。
さらに、2020年に始まった新型コロナウイルスの感染拡大による巣ごもり需要によってさらに拡大、現在も拡大傾向にあります。
このように、EC市場の拡大に伴い取扱物量が増加し、特に個口配送を主軸とする物流会社にとって大きな負担となっています。
労働時間の規制強化
2024年4月から始まったドライバーに対する時間外労働の上限規制により、原則として月45時間、年間360時間(労使協定締結時は960時間)に制限されるようになりました。
さらに、2025年の法改正によって荷役待機時間の1運行2時間ルールが定められ、ドライバーを管理・監督する企業にはより厳しい法令遵守と、厳しい規制のなかでも増加し続ける物量への対応が急務となっています。
ドライバー不足と労働人口の高齢化
物流業界に限らず、多くの企業が少子高齢化による労働人口減少という課題を抱えています。
物流業界の現場では、肉体的負担や運転に伴う精神的負担の大きさが人材不足に拍車をかけ、既存路線の確保や新規路線の拡大が困難な状況となっています。
コストの高騰
物価高に伴う燃料費や車両維持費などの負担が、物流会社の資金面に重くのしかかっている状況となっています。
また、2021年以降上昇を続ける最低賃金や物価高騰に対応するための賃金引き上げも負担の一つです。
物流クライシスが与える影響
物流クライシスは、以下のように物流会社はもちろん、荷主・荷受側へ大きな影響を及ぼす可能性があります。
輸送サービスの品質低下
物量が増加し続けているにも関わらず法規制や人材不足によって輸送が追いつかなくなった場合、遅延をしたり、これまでの輸送に必要な日数が維持できないなど、輸送サービスの品質の低下を招く恐れがあります。
人手不足倒産の増加
帝国データバンクの調査によると、2024年度に全産業を通じて人手不足が原因で倒産した企業の件数は350件と、過去最多を記録しています。
なかでも物流業を営む企業の件数は42件あり、1位である建設業の111件に次ぐ件数となっています。
このような背景から、人手不足の解消は企業としての生き残りが関わる重要な課題といえるでしょう。
参考:帝国データバンク|人手不足倒産の動向調査(2024年)
荷主企業の競争力低下
ECサイトで購入した製品が届かないことによる信用の低下、材料が届かず工場の稼働に遅れが生じて販売に間に合わないなど、物流に滞りが生じると荷主企業の競争力低下につながる恐れがあります。
荷主の競争力低下の原因が物流にある場合、状況によっては取引がなくなってしまうなど、経営状態の悪化を招くリスクがあります。
社会インフラへも影響を及ぼす可能性がある
輸送能力の低下によって生活必需品の流通が滞ったり、物流に関連するサービス(ガソリンスタンドや高速道路の利用など)の売上低下など、さまざまな面に影響を及ぼす可能性があります。
その結果として、すでに問題となっている物価がさらに高騰する可能性もあるでしょう。
また、車両不足を補うために小口のトラック便が増加した場合、交通渋滞を招くといったことも考えられます。
物流クライシスはいつまで続く?
さまざまな面への影響が考えられる物流クライシスがいつまで続くのか、気になる経営者の方は多いのではないでしょうか。
2024年問題や2025年問題の続きとして「2027年問題」というものがあり、多くのドライバーが定年退職に伴う離職をすることが予測されています。
また、経営コンサルティングファームのボストン コンサルティング グループが過去に行った調査によると、2027年のドライバー不足は24万人にのぼり、物流業界が危機的状況に陥るといった結果が公表されています。
上記以外にも、経済産業省によって2030年には輸送力が約34%(およそ9億トン相当)不足することが発表されていることから、今後数年の間は物流業界にとって大きな課題が残るといえるでしょう。
参考:ボストン コンサルティング グループ|2017年プレスリリース
参考:経済産業省|物流を取り巻く現状と取組状況について
物流クライシスを乗り越えて生き残る方法
解決しなければ、自社の存続危機や社会への影響など、さまざまなリスクが生じる物流クライシスを乗り越える方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
以下の3つのポイントに焦点を当てて解説します。
DX化による業務効率・生産性の向上
物流会社ができるDX化の例として、配車や点呼などの事務的業務のデジタル化による業務効率の向上が挙げられます。
また、ヤマト運輸株式会社の「YAMATO NEXT 100」のようにAIなどのシステムを活用して事業所の業務量を算出し、経営資源の適切な配置やコストの最適化を行う取り組みも今後必要となるでしょう。
その他にも、予約システムの導入による待機時間の削減など、車両だけでなく荷積・荷下ろしに関する取り組みも必要です。
参考:ヤマトホールディングス株式会社|TRANSFORMATION PLAN “YAMATO NEXT100” ~GRAND DESIGN~
物流標準化やデータ連携の推進
国土交通省により、パレットや外装の標準化、伝票や商品データなどに関するシステム間の相互連携といった取り組みが進められています。
これらは荷主側に対する課題と思われがちですが、物流会社側としても内容を理解し、荷主側と連携をとり、協力体制をより強固にすることが求められます。
M&Aの実施
近年では、抱えている課題を解決する方法としてM&Aを行う物流会社も増加しています。
M&Aによって対象企業を取り込むことにより、人材と車両の両方を獲得し、ドライバー不足の解消を目指すことが可能です。
また、すでに開拓されている既存路線も獲得でき、経営基盤の強化と市場拡大を目指すこともできます。
その他のM&Aのメリットとして、物流クライシスが原因で悪化した経営の売却をすることにより、企業を存続させ、これまでともに頑張ってくれた従業員の雇用を守ることができます。
まとめ
物流クライシスは、社会の製品流通を担う物流会社にとって大きな問題です。
課題を解決して企業を存続させなければ、経営状態の悪化を招き、会社を支えてくれた従業員が仕事を失ってしまうリスクが高まります。
さらに、物流会社が減少することで物質が滞り、人々の生活に大きな障害をもたらす可能性もあるでしょう。
このような大きな問題を乗り越え、企業を、そして物流インフラを守る方法の一つがM&Aです。
M&Aを実施することにより人材の確保や相手企業の保有する既存路線を獲得することで、ドライバー不足の解消や市場拡大など、さまざまなメリットを得ることができます。
売り手企業側としては、自社を存続させ、大切な従業員の雇用も維持することが可能です。
物流クライシスを乗り越え、「自社のさらなる発展を目指したい」「従業員の雇用と物流インフラを守りたい」とお考えの方は、まずはお気軽にM&Aベストパートナーズへご相談ください。
物流業界に精通した専任アドバイザーが課題と目的を丁寧にヒアリングし、物流クライシスを乗り越えるための方法のご提案をさせていただきます。
こちらの関連サイトでは、物流業界が抱える課題解決に向けたサービスをご提供しておりますので、あわせてご覧ください。