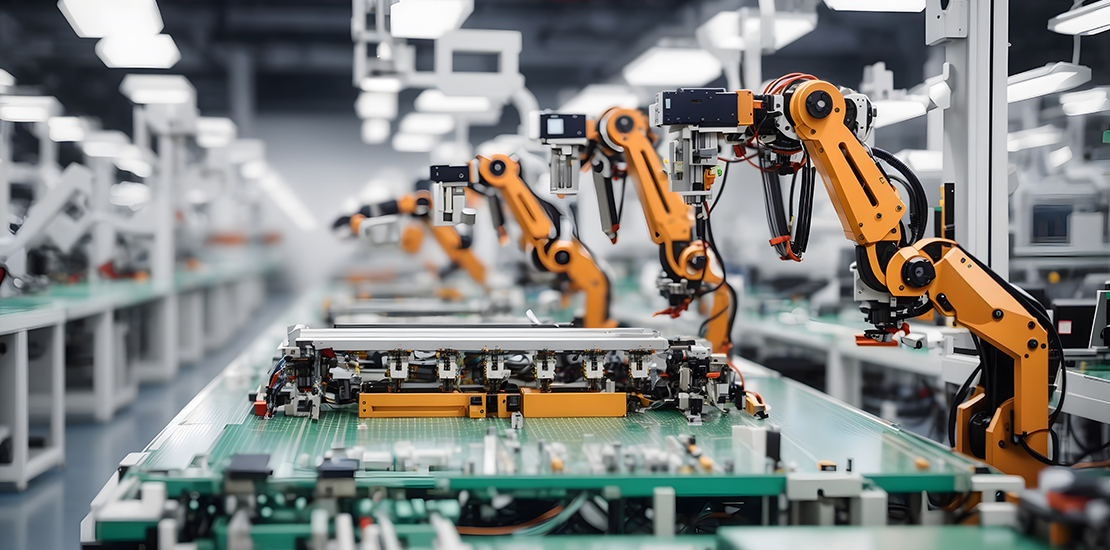島国である日本にとって、豊かな海産物は国の強みであり、食生活を支える大切な資源でもあります。海産物を社会に提供する役割を担う水産業は、日本に欠かせない産業です。
しかし、昨今の水産業にはさまざまな課題が存在し、廃業の危機に直面している会社も多いでしょう。
日本の水産業を守るうえでは、課題やその解決策について理解を深めることが重要です。本記事では、水産業が抱える課題や期待される取り組み、解決策について詳しくお伝えします。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
水産業が抱える課題
まずは、現状の水産業が抱える課題について把握しておきましょう。
ここでは政府のデータを交えながら、水産業における4つの課題を紹介します。
漁獲量減少への対策
水産業の大きな課題となっているのは、漁獲量減少への対策です。
水産庁の「数字で理解する水産業」によると、日本の漁業における生産量は1980年代ごろから減少しています。1984年のピーク時は1,282万トンだったのが、2018年には442万トンです。
生産量が半分以下にまで落ち込んでいる原因は、漁場環境の悪化や魚介類の乱獲などが考えられます。水産業にとって漁獲量の減少は、売り上げの減少につながる深刻な問題です。
そのため持続可能な漁業の実現に向けた、水産資源の保全活動が求められています。
魚介類の国内需要回復
落ち込んだ魚介類の国内需要を回復させることも、水産業にとって大切な課題です。
同じく、水産庁の「数字で理解する水産業」よると、日本国内の魚介類消費量は2000年ごろから減少が続いています。2001年度には1人あたり年間約40kgの魚介類を消費していたのが、2018年度には約24kgと、約6割にまで低下しました。
日本人の魚介類消費が落ち込んでいる原因は、食の多様化による部分が影響しています。食に対する選択肢が多様化したことが、魚介類の消費低下につながっているといえるでしょう。
「国内の需要が低下しているなら、海外への輸出をすれば?」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、海外へ向けた輸出は世界情勢の影響を受けやすく、不安定になりがちです。
水産業が安定した売り上げを確保するためには、国内需要を大切にすることが必要です。
人手不足の解消
水産業では、人手不足も課題となっています。
水産庁の「水産業の就業者をめぐる動向」によると、漁業就業者数は2000年ごろから減少を続けています。2003年には約24万人いた漁業就業者が、2020年には13.6万人にまで減少しました。
人手不足の原因として、日本全体で労働人口が減少していることが挙げられます。水産業における待遇の改善やイメージアップなど、水産業従事者を確保するための施策が必要です。
後継者の確保
さまざまな業種で問題となっている後継者不足は、水産業でも起こっています。後継者を確保できないとき、廃業のリスクもあるでしょう。
内閣府による「我が国水産業の現状と課題」によると、漁業就業者の平均年齢は2016年時点で56.7歳と、高齢化が進んでいます。若年層の雇用確保ができず、事業を続けたとき、廃業のリスクはより高くなるでしょう。
日本の水産業を守るためには、後継者を確保して水産業を絶やさないことが重要です。
水産業の課題対策として行われている主な取り組み
さまざまな課題のある水産業に対して、政府は積極的な取り組みを行っています。
水産業の課題対策として政府が行っている主な取り組みは、次の3つです。
それぞれの取り組みについて詳しく解説します。
新しい資源管理の推進
漁獲量の減少を防ぐためには、水産資源の管理が重要です。
2020年、水産庁は水産資源管理の適正化を図るために「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」を作り、具体的な資源管理の推進計画を公表しました。
例えば、TAC(漁獲可能量)の管理対象となる魚種が拡大されました。TACの拡大によって漁獲量上限を厳格に管理し、過剰な漁獲の防止を目指しています。
新しい資源管理の推進は、漁獲量の管理や適正化が期待できる施策といえるでしょう。
密漁や不正な漁業の取り締まり強化
法律による許可を得ていない密漁・不正漁業は、漁獲量や国際競争力に悪影響を及ぼしかねません。そのため、政府は密漁や不正な漁業の取り締まりを強化しています。
また、IUU漁業(違法・無報告・無規制な漁業)によって水揚げされた水産物の流通を防ぐための規制も強化しています。
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」では、IUU漁業のリスクが高い魚種の輸入に対して、外国政府機関の証明書の提出が義務付けられました。
さまざまな施策よって国内水産物は保護され、値崩れの防止にもつながるでしょう。
漁場環境の保全活動
水産資源を守るうえでは、漁場環境の保全も大切です。そのため、政府は水産資源の生育にとって重要な藻場や干潟の保全に向けた活動も推進しています。
例えば、稚魚をある程度の大きさまで人工的に育成してから放流する「種苗放流」を行うことで、稚魚が過剰に捕食されることを抑制できます。種苗放流によって生き残る生体が増えれば、水産資源の増加につながるでしょう。
また、海洋ごみの誤食も、水産資源が減少する原因です。ゴミの誤飲による水産資源の減少を防ぐため、科学的調査や各地での回収が推進されています。
水産業者が課題を乗り越えるための解決策
水産業が抱える環境面や国際的な課題については、政府による積極的な取り組みによって改善が期待でしょう。
一方で、人手不足解消や後継者確保など、事業の継続に関する課題については各水産業者による対策が必要です。
水産業者が抱える課題を乗り越えるための方法を2つご紹介します。
DXの推進
水産業者の人手不足を解消するうえでは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が重要です。
DXとは、デジタル技術の活用を通じてビジネスの変革を図る取り組みを指します。DXを推進することで、水産業者の生産性向上につながるでしょう。
例えば「陸上養殖システム」を導入することで、養殖魚をカメラで監視したり、センサーから自動取得したデータを管理したりできます。
デジタル技術によって既存人材の負担が軽減できれば、人手不足を緩和する効果が期待できるでしょう。
政府も「スマート水産業」を推進しているため、今後は水産業者においてDXが浸透していくと予測できます。
M&Aの実施
人手不足や後継者問題の解消を図るべく、「M&A」を実施する水産業者も増えています。
M&Aは、合併(Merger)と買収(Acquisition)を合わせた言葉で、複数企業の統合を軸とした経営戦略のことです。
M&Aによって適切な相手企業と統合すれば、両社が単独でいるよりも成果が高まる「シナジー効果」が期待できます。
M&Aにはさまざまなメリットがあるため、水産業においても有力な解決策となるでしょう。
水産業の課題解決のためにM&Aを実施するメリット
M&Aは、水産業だけでなくさまざまな業種で課題を解決するための方法として注目されています。
水産業の課題解決にあたってM&Aを実施する主なメリットは次の3つです。
それぞれのメリットについて詳しくご紹介します。
後継者不足の解消
後継者不足で悩まれる水産業者の方は少なくありません。
M&Aをすることで、廃業せずに事業の継続をすることが可能になります。新たな経営者に事業を引き継ぐことで、培ってきた技術のノウハウを失うリスクも回避できます。
また、債務の個人保証を抱えている経営者も少なくありません。個人保証をしている場合、廃業時に経営者は会社の債務を支払うことになります。
しかし、交渉次第で債務の個人保証を解消できる可能性があることも、M&Aのメリットといえます。
人手不足の解消
労働人口自体が減少するなかで、人材雇用を強化することは容易ではありません。
しかし、M&Aを行うことで自社と相手企業の人材を統合し、新たな組織体制の構築が可能です。相手企業の従業員を取り込むことで、人手不足の解消が見込めます。
また、買手側となる企業は、M&Aによって人材を確保することにより、採用活動や教育にかかるコストの削減ができることも大きなメリットです。
事業の拡大・多角化が図れる
M&Aは、事業の拡大・多角化を目指すためにも有効な方法です。
同じ水産業者と統合することで、取引先や漁場の統合により事業の拡大が図れます。また、他業種の会社と統合すうることで、自社にはない事業を取り込み、迅速に多角化を実現する効果が期待できます。
事業の拡大や多角化をする場合、設備の導入や人材確保など、多くの手間とコストが生じます。
しかし、M&Aによって相手企業の経営資源を取り込むことができれば、余計な手間やコストを抑えられるでしょう。
M&Aを成功させるためのポイント
M&Aは水産業の課題解決に向けて有効な方法ですが、ポイントを押さえなければ成功させることは難しいです。
水産業者がM&Aを成功させるためのポイントは、主に次の3つです。
M&Aの目的・戦略を明確にする
M&Aを検討するとき、はじめに目的や戦略を明確化することが大切です。
M&Aには事業拡大や人手不足解消など、さまざまな目的があり、事業者によって異なります。目的が不明確なままM&Aの検討をした場合、適切な手法の選択ができず、その後の戦略にもブレが生じます。
M&Aの検討をするときは、初めに目的を明確にし、それに合った戦略を決めましょう。目的や戦略が具体的になれば、M&Aの相手企業とのマッチングもしやすくなります。
自社の価値を把握・向上させる
好条件でM&Aを実施するには、自社の価値を正しく把握し、現状よりも価値を向上させることが大切です。
価値の把握をするときは、財務状況だけでなく、自社だけの強みや弱みなども明確にしましょう。
M&Aの契約条件は、買い手と売り手が交渉を行うことで決定されます。自社の価値が低いとみなされた場合、買い手企業に低い取引金額を提示される可能性は否定できません。
また、自社の価値を正しく把握していないと提示金額の根拠を示すことができず、スムーズな交渉が難しくなります。
スピーディなM&Aを実現するためにも、客観的に自社の価値を把握しましょう。
その他に、債務があれば整理したり、ブランド力を高めたりすることも有効です。
専門家のサポートを受ける
M&Aの知識や経験がない水産業者が、適切にプロセスを進めることは容易ではありません。
M&Aには計画や相手企業探し、交渉、契約手続きなど、多くのプロセスがあります。税務や法務といった知識も要求されるため、M&Aの成功には専門家のサポートが不可欠です。
M&Aの経験や実績の豊富な専門家によるサポートがあれば、抱えている悩みに対して適切なアドバイスを受けることができます。また、交渉や複雑な手続きにも対応してくれます。
M&Aの検討をするときは、専門家によるサポートを受けることがおすすめです。
まとめ
日本の食生活を支える水産業には、漁獲量減少への対策や魚介類の国内需要回復など、さまざまな課題があります。
政府による新しい資源管理の推進や漁場環境の保全活動といった取り組みも、すべての課題を解決できるものではありません。
人手不足解消や後継者確保といった課題を解決するためには、各水産業者が抱えている課題に取り組むことが必要です。状況によっては、M&Aという方法も選択肢に加えてもいいでしょう。
しかし、M&Aを実行するためには、知識やノウハウがなければ成功させることは難しいです。
M&Aベストパートナーズでは、これまでさまざまな業種におけるM&Aを成功に導いた実績と知識がございます。
水産業の課題解決に向けたM&Aを検討されるときは、M&A・事業継承の実績が豊富な「M&Aベストパートナーズ」へお気軽にご相談ください。