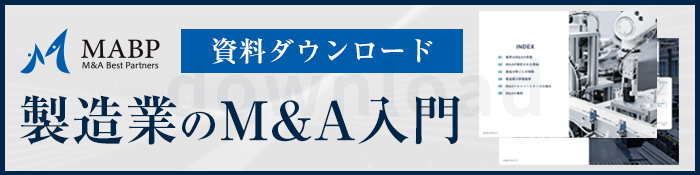電機業界は、技術の革新と市場の動向によって時代とともに変化しています。
近年では、激しくなる市場競争への対応や後継者問題など、さまざまな課題を抱えています。
この記事では、電機業界が抱える課題と解決策について、M&Aの専門家が詳しく解説します。
経営基盤の強化や市場拡大、事業の継続などで悩みを抱えている経営者の方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
電機業界の現状と市場動向
電機業界には家電やOA機器・半導体など、さまざまな分野があり、日本国内の産業内では2番目の市場規模を誇っています。
大きな市場をもつ電機業界の現状や市場動向について、詳しく解説します。
国内需要の鈍化
少子高齢化の影響を受け、国内需要の鈍化が懸念されています。また、海外製品の販売が好調なことも、国内製品の市場圧迫につながっています。
なかでも家電分野は国内需要に支えられています。今後も人口減少が続くことが予測できるため、減少に比例して家電の買い替えや新たな購入に影響を与えるでしょう。
サプライチェーンの複雑化
電気製品は複数の工程を経て製造されています。さまざまな部品や素材を扱うため、サプライチェーンが複雑化しています。
製品や使用する部品の多様化が課題となっているため、サプライチェーンの効率化は早急に対応すべき課題となっています。
課題解決に向けて、次のような対応が求められます。
- IoTやAI、ビッグデータ等のデジタル技術を活用した「スマートマニュファクチャリング」の実現
- 製品製造における情報や業務の一元管理できるシステムの導入
- AI技術を活用した需要の予測モデルを導入する
置かれている状況によって必要な対応は異なりますが、今後市場で生き残るためには、業務管理システムなど新たな導入の検討が必要です。
電機業界が抱える課題
市場競争が激しさを増している電機業界では、解決すべき課題があります。課題解決に向けた対策を早急に行わない場合、経営状況の悪化や廃業など、さまざまなリスクが生じます。
電機業界が解決すべき課題について、詳しく解説します。
DX化の推進による生産性の向上
電機業界における日本の技術力は、世界でもトップクラスの実力を誇っています。一方で、生産効率を考えた場合、海外の大手企業と比較すると劣ってしまうことが実情です。
そのため、海外企業との競争に打ち勝つためにはIoTやAI技術を導入し、生産効率の強化が必要です。
新たなシステムの導入には時間とコストがかかりますが、効率のよい生産体制の構築ができれば、コスト削減や新製品の開発に時間を使うことができるでしょう。
新しい市場の開拓
国内需要の減少への対策として、海外に新たな市場を求める企業が増えています。日本国内の人口減少は歯止めの効かない状況のため、海外へ進出することは自然なことでしょう。
しかし、新たな市場の開拓は多くの時間とコストを必要とします。市場開拓に向けた従業員の雇用拡大や育成も必要です。
どのようにして効率よく新しい市場を開拓するかは、電気業界に関わる多くの企業が抱えている課題といえます。
後継者不足
後継者不足は、電機業界に限らずさまざまな業種が抱えている課題です。
後継者不足の原因として、親族が事業の引き継ぎを拒否することや、経営に関するスキルをもつ従業員がいないなどが挙げられます。
経営者が引退したくても後継者が見つからない場合、事業の継続が困難になり、廃業のリスクも生じます。
長年積み上げてきた技術やノウハウを失うことは、ものづくり大国とも呼ばれる日本では大きな痛手となるでしょう。
電機業界の課題解決に向けたM&Aの動向
電機業界では、課題解決のためにM&Aが活発に行われています。
例えば、新たな設備を導入するための資本が足りず、大手企業の傘下に入ることで資金調達がしやすくなります。
また、新たな市場開拓を目指す企業が他企業を統合し、相手の市場へ参入しやすくするためにM&Aを行うケースがあります。
後継者問題で廃業せざるを得ない企業が、技術やノウハウを存続させ、従業員の雇用を維持するために事業を売却するケースもあります。
M&Aをする理由は企業によってさまざまですが、電機業界では多くのM&Aが行われています。
電機業界におけるM&Aのメリット・デメリット
M&Aを行うことは課題解決に向けた有効な方法といえます。しかし、デメリットも存在し、把握しておかないとM&Aで得られる効果が低くなる可能性があります。
売り手側と買い手側の視点から、メリットとデメリットをご紹介します。
売り手側のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| 後継者問題の解決 | 条件次第では譲渡先が見つかりにくい |
| 従業員の雇用維持 | 希望する条件での売却ができない可能性がある |
| 財務の健全化 | 既存取引先や顧客に不安や不信感を与える |
| 新規事業に向けた資金調達 | 従業員のモチベーションが下がる可能性がある |
| 個人保証からの解放 | 交渉の中断や白紙になる可能性がある |
後継者問題の解決や資金調達、個人保証からの解放など、M&Aは売り手企業にとって多くのメリットをもたらします。
一方で、適切な条件設定がされていない場合、譲渡先が見つからなかったり、希望額での売却ができなかったりするなどのデメリットがあります。
買い手側のメリット・デメリット
買い手側のメリットは、以下のようなことが挙げられます。
- 技術やノウハウの獲得
- 優秀な人材の確保
- 新規事業(市場)への参入がしやすくなる
- 複数の事業展開によるリスク分散
M&Aをすることで、売り手企業が積み上げてきた技術やノウハウ・優秀な人材を獲得し、自社の技術力をさらに高める効果が期待できます。
また、新規市場への参入も、スムーズに行うことがああできるでしょう。
一方で、契約締結前に相手の企業調査(デューデリジェンス)を入念に行わなかった場合、契約後に虚偽申告や負債が発覚するケースも少なくありません。
M&Aをする際は企業調査をしっかり行い、締結後のトラブルを回避することが大切です。
電機業界でM&Aをするときの注意点
M&Aを実行に移す場合、メリット・デメリットの把握は重要です。しかし、それだけではM&Aを成功に導くことはできません。
M&Aを実行するうえで注意すべき点について解説します。M&Aを検討し、実行に向けた行動をする前に確認してください。
目的を明確にする
「なぜM&Aをするのか」と、目的を明確にしてください。
例えば、売り手側であれば「後継者がいないから事業を譲渡したい」や「設備投資をするために大手の傘下に入りたい」といった理由があるでしょう。
買い手企業の場合は、「新たな技術を獲得したい」や「市場拡大」などの目的が挙げられます。
M&Aを考える最初の段階で明確な目的を設定しない場合、実行途中で行き違いが生じ、失敗に繋がるケースは少なくありません。
適正な価格を提示する
譲渡価格を検討するとき、自社に対する思い入れの強さから過大評価をする経営者は少なくありません。しかし、買い手企業がその価値に納得できなたかった場合、売却先が見つかりにくくなるケースがあります。
M&Aで事業譲渡などを行なう場合、客観的な視点で適切な評価額を設定してください。売却先の選択肢が広がり、交渉もスムーズに行なうことができるでしょう。
統合プロセス(PMI)を適切に行う
M&Aの締結後に行なうPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)を適切に行なうことで、シナジー効果を高めることができます。
企業文化やシステムの統合、組織の再編成を円滑に行うことで、従業員の不安や悩みを解消し、モチベーション向上につながります。
電機業界で売却価格を算出する方法
M&Aによって事業の売却価格を算出する方法は3つあります。
それぞれの算出方法をご紹介します。
コストアプローチ
コストアプローチは、純資産をもとに企業価値を算出する方法です。
中小企業の売却でよく用いられており、年買法※1を適用するのが一般的です。
※1:時価純資産※2+営業利益の2~5年分
※2:時価資産-時価負債
すべての資産・負債を時価評価するのは不可能なため、不動産や有価証券など、価格が変動しやすいものに焦点を絞って時価評価を算出するのが一般的です。このとき、ノウハウや人材などに対する評価は含みません。
インカムアプローチ
インカムアプローチは、中堅及び上場企業、ベンチャー企業が譲渡企業側となる場合、あるいは買収企業側が上場企業となる場合に用いられる方法です。
算出にはDCF法を用いるのが一般的とされています。
DCF法は、事業によって生み出されるキャッシュフローをもとに株式価値を評価します。
- 約5~10年分の事業計画をもとに、納税や事業活動への投資分を除いたフリーキャッシュフローを算出
- フリーキャッシュフローから、現在価値に直して合計した事業価値を算出
- 事業価値に事業外資産を加算して、株式価値を算出する
この方法は予測と主観が基準になっている面が強く、マーケットアプローチと併用するのが一般的です。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチには、市場株価法と類似会社比較法があります。
市場株価法は、売り手側が上場企業の場合に用いられ、株式時価総額をベースに企業価値を算出します。株価の変動を考慮し一定期間の平均株価を参考にしたり、支配権プレミアムとして株式時価総額の2割程度を上乗せしたりするのが一般的です。
類似会社比較法は、売り手側が非上場企業の場合に用いられ、事業の内容・状態が類似している上場企業と比較することで、企業価値を算出する方法です。
しかしこの方法は、類似した上場企業が見つからないことも多いため、あまり用いられることはありません。
電機機器業界のM&A事例
ここからは、実際のM&Aの経験や事例を2つ、ご紹介します。
また、それぞれのM&Aストーリーへのリンクも記載していますので、電気機器業界のM&Aについての実例を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
【配電盤・分電盤・制御盤の設計/製作】松栄電機株式会社様の事例
松栄電機株式会社様は、1941年3月創設、1955年に株式会社となった電気製造業の会社。三代目社長である新堀英世氏が父親から会社を継いだ時、業績は順調でした。
それでも、40代半ばでM&Aを検討します。理由は、事業継承者がいないこと、娘2人のためにも準備は万全にしておく必要性を感じたこと、起業意識や、事業拡大という目標もあったことなど。
コロナ禍の影響もあり、経営が成り立たなくなる懸念もありました。
それらの課題を一気にまとめることができるのがM&Aだったのです。
担当となったMABPのM&Aアドバイザー・石田功は、松栄電機株式会社様と同様、製造業出身でした。新堀氏は、それが心を開ける大きな理由となったと言います。
石田は新堀氏の要望に応えつつ、複数の会社を紹介。新堀氏はその中の一社とM&Aのトップ面談まで至り、そこからは半年で最終契約を結びました。
「十社も当たれば、たいていの傾向がわかります」
信頼できるM&Aアドバイサーを探すポイントとして、「データをできる限り集めること」だと新堀氏はアドバイスしています。
そして「知識をある程度持っておき、わからないことは専門家に聞くようにすれば、舵を大きく取り間違えることはなく、気持ちも負けないと思います」と締めくくりました。
【電気設備設計施工等、電気工事全般】株式会社ひかりシステム様の事例
株式会社ひかりシステム様は、1956年創業のひかり電気商会から始まり、有限会社ひかり電気を経て、1991年、現在の株式会社ひかりシステムとなり、狩野宏氏が社長に就任しました。
創業当時は、いわゆる「町の電気屋さん」で、今も電気工事を数多く手掛ける会社。そのため、従業員の約8割は、電気工事士などの職人集団です。狩野氏にとっては信頼できる仲間たちですが、優秀な職人が優秀な社長になれるとは限りません。
狩野氏は、後継者について悩んでいました。息子を後継者にする手もありましたが、年上で経験豊富、しかも職人肌で癖の強い従業員たちを指揮するのはおそらく難しい。そうして狩野氏は、M&Aを検討するようになりました。
会社のいいとこ取りをされるのではという心配が強かった狩野氏ですが、MABPの桶谷祐太の仲介のもと、医薬・化学・食品・製紙プラント会社を中心に、配管・製缶・機械装置・空調・メンテナンスなど、さまざまな生産設備のサポートを行う株式会社望月工業所様の代表取締役・望月達也氏と出会い、トップ面談へと至ります。
職人出身の狩野氏にとって、そうでない望月氏とは、正確や考え方の相違があるのではという懸念がありましたが、望月氏の勤勉な姿勢に惹かれ、尊敬の念を抱くようになったことから、M&Aの話を前に進めることとなりました。
まとめ
電機業界は、時代の流れとともに新しい技術や製品が開発され、企業間競争が激しくなっています。また、日本国内の人口減少や物価高の影響もあり、需要と虚いう急のバランスが崩れ、競争をより激化させています。
市場内での競争に打ち勝ち、事業を継続させるためにはM&はとても有効な方法です。
事業の継続だけでなく、新たな技術やノウハウの獲得、市場拡大などさまざまなメリットがあります。
しかし、M&Aは慎重に相手を選ばないとシナジー効果を高めることができません。また、評価額の算出や複雑な手続きなど、専門的知識と経験が必要です。
私たちM&Aベストパートナーズは、製造業をはじめ、これまでさまざまな業種のM&Aサポートを行ってきた実績がございます。
M&Aを検討している電機業界の経営者の方は、まずはお気軽にM&Aベストパートナーズへご相談ください。
悩みや課題をお伺いし、最適なご提案をさせていただきます。