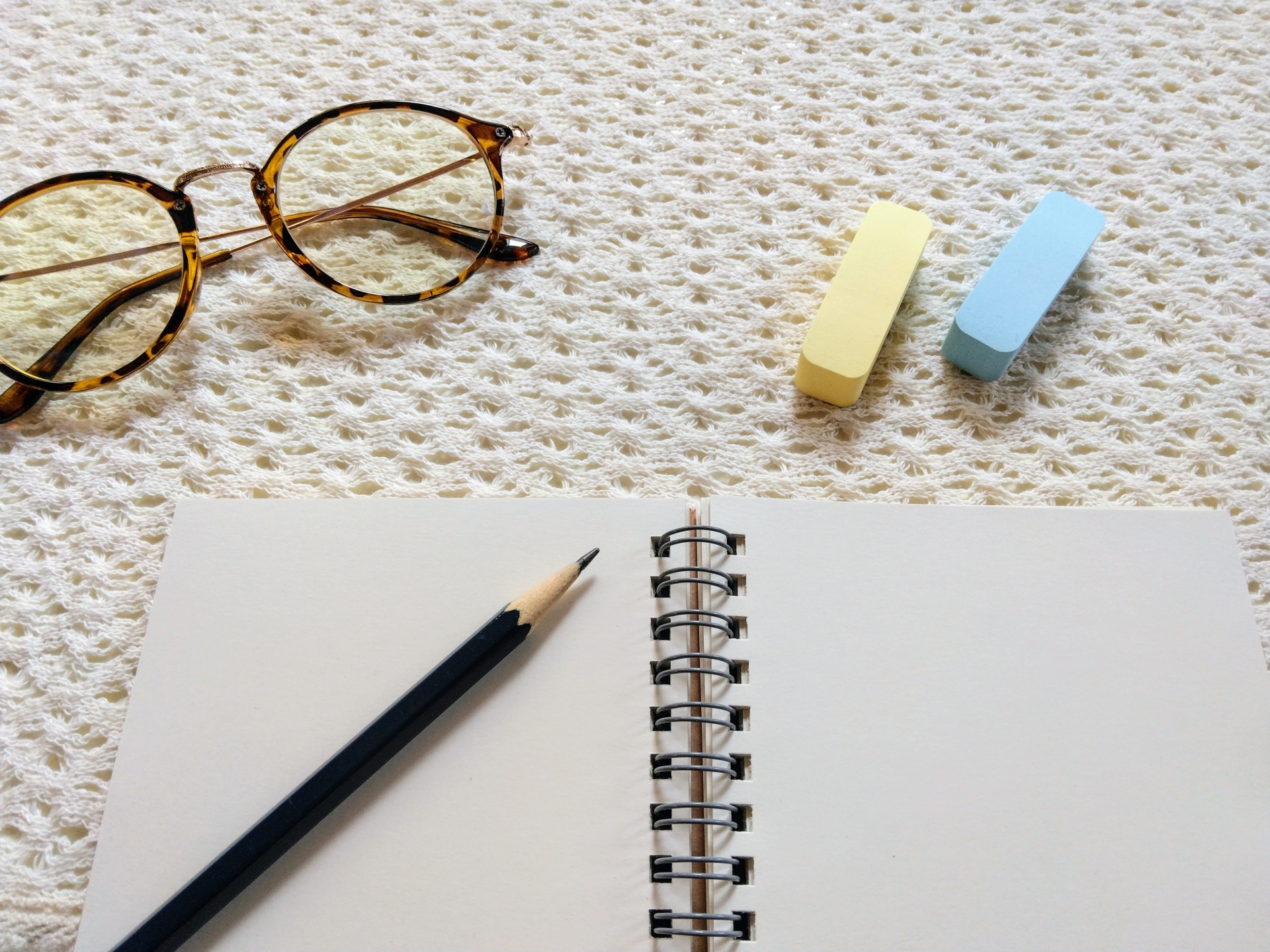M&Aを検討する場合、M&A仲介会社から総合的なサポートを受ける「アドバイザリー契約」を締結するのが一般的です。
そこで本記事では、M&Aのアドバイザリー契約とはどのようなものかを詳しく解説します。また、顧問契約やコンサルティング契約との違い、交渉方式・報酬体系・アドバイザリー契約の流れも解説するので、M&Aを検討されている方はぜひ参考にしてください。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
アドバイザリー契約とは
アドバイザリー契約とは、専門性の高い分野において外部の専門家や事業者から助言・提言を受けるための契約です。
M&Aを実行するためには経営実務・経営戦略から財務・法務・税務に至るまで、深い知識を必要とします。
また、候補先企業の価値を見極めて相手企業の調査を行うなど、幅広い専門的な知識や経験が不可欠です。
買い手となる企業の場合には、買収を検討している企業との条件交渉なども必要です。
M&Aにおけるアドバイザリー契約では、M&A仲介会社や金融機関などとアドバイザリー契約を結び、上記のようなM&Aに関連する総合的なアドバイスやサポートを受けることが可能となります。
アドバイザリー契約の形態
アドバイザリー契約は、大きく「専任契約」と「非専任契約」の2つの契約形態に分けられます。
- 専任契約:
1社のM&A仲介会社とアドバイザリー契約を行う - 非専任契約:
複数のM&A仲介会社とアドバイザリー契約を行う
専任契約のメリットは、M&Aを1社のみに任せるため情報漏洩のリスクを低減できることです。また、1社と緊密な連携を図ることから、丁寧なサポートを受けられることもメリットです。
一方の非専任契約は、複数の業者にマッチングを依頼することによって買い手企業を短期間で見つけられるメリットがあります。
専任契約・非専任契約にはデメリットもあるため注意が必要です。
専任契約の場合、担当者と相性が合わないとスムーズなM&Aが行えない可能性があります。
非専任契約のデメリットとして、複数の業者に情報を提供することによって情報漏洩のリスクが高まる点が挙げられます。
また、専任契約と比べて担当者のモチベーションが上がらず、細やかなサポートを受けられない可能性も考えられます。
アドバイザリー契約と他の契約の違い
アドバイザリー契約と類似する契約として、以下の3つが挙げられます。
- 顧問契約
- コンサルティング契約
- 業務委託契約
アドバイザリー契約と各契約の相違点を解説します。
顧問契約との違い
顧問契約とは、特定分野において専門的な知識・経験を持つスペシャリストに相談し、サポートを受ける契約です。
顧問契約の契約対象は専門家が得意とする分野のみとなり、業務範囲は限定的であるケースが多いです。
契約期間が長期に渡ることが前提条件となっており、契約期間中は専門家に対して毎月顧問料として報酬を支払います。
一方のアドバイザリー契約は、M&Aの実現に向けてサポートを受けるための契約です。
そのためアドバイザリー契約の対象期間はM&A成立時までとなります。
報酬面にも違いがあり、顧問契約では毎月の顧問料が発生するのに対し、アドバイザリー契約の場合は契約形態やM&A仲介会社によっては月額報酬が発生しないケースがあります。
コンサルティング契約との違い
アドバイザリー契約とコンサルティング契約との大きな相違点は、アドバイスの対象範囲です。
アドバイザリー契約では依頼企業の将来に対して財務・税務・法務などの視点から助言・提言を行うため、アドバイスの対象範囲は広くなります。
一方、コンサルティング契約は依頼企業が既に抱えている企業の経営課題を発見し、その解決のためにアドバイスを行います。そのためアドバイスの対象範囲は限定されたものとなります。
業務委託契約との違い
業務委託契約は、自社では対応が難しい特定の業務を外部へ委託する際に締結し、その業務遂行に対する成果として報酬が支払われます。
委託した業務の完了に対して報酬が支払われた時点で契約が終了するため、アドバイザリー契約と同じような契約といえるでしょう。
アドバイザリー契約書の内容
アドバイザリー契約を締結する場合、依頼する企業はM&A仲介会社と「アドバイザリー契約書」を作成・締結をします。
契約書に盛り込むべき項目を解説します。
契約締結の対象企業
はじめに、契約締結の対象企業を以下のように明確にします。
〇〇株式会社(以下「甲」という。)とM&A〇〇株式会社(以下「乙」という。)と乙が甲に紹介する候補企業(以下「丙」という。)とは、甲による企業連携の交渉・契約の締結(以下「本提携」という。)に関し、次の通り契約(以下「本契約」という。)する。
誰と誰を結ぶ契約なのか、契約の対象企業を明確にしてください。
業務内容と範囲
アドバイザリー契約では、不明確な業務範囲を規定したり、特定した内容が不十分であったりすると、業務に支障が生じるおそれがあるため、業務内容や範囲を明確にしておくことが重要です。
具体的には以下のような業務が発生します。
- 候補先企業の調査、選定、紹介
- 交渉や各手続きに係るスケジュール調整
- 企業評価に係るアドバイス
- 候補先企業との交渉時の立会
- 条件交渉
- 各種資料の作成
- 公認会計士や税理士、弁護士などの専門家の紹介
- デューデリジェンスの調整など
契約書で責任範囲を明確にしておくことは委託者・受託者双方にとって非常に重要なので、必ず規定するようにしましょう。
報酬体系と費用
M&A仲介会社によって、アドバイザリー契約で発生する報酬は異なります。
着手金・中間報酬金・月額報酬金・成功報酬金など、採用する報酬体系について、契約書に盛り込みましょう。
- 着手金:
アドバイザリー契約時に支払う手数料。着手金の費用相場は50万〜200万円程度が一般的。 - 中間報酬金:
M&Aが進む中で「基本合意書」の締結時に支払う手数料。成功報酬の一部の先払いの意味を持つ。相場は成功報酬の10%〜20%程度。 - 月額報酬金:
業務に対して毎月支払う手数料。月額100万円〜300万円が相場の目安。 - 成功報酬金:
M&A成立時点で支払う費用。M&Aの取引金額に一定の報酬率を乗じる「レーマン方式」により算出された金額を支払う。
報酬とは別に、候補先との交渉のための交通費や出張費、官報に公告を載せる際の公告掲載料など、M&A業務を行う際に発生する費用をどうするかについても明記します。
M&A業務に伴う費用は依頼する側が支払うことが一般的ですが、具体的に明記することでその後のトラブルを回避することが可能です。
秘密保持
秘密保持に関する事項として、情報管理の方法や禁止事項について定めたものを明記します。
秘密保持契約を定める理由は、M&Aを実施するには売り手企業がM&A仲介会社に対して秘匿性が高い情報を提供する必要があるためです。
M&A業界には「秘密保持に始まって秘密保持に終わる」という有名な言葉があるほど、秘密保持は非常に重要です。
秘密保持契約の対象範囲、機密事項の取り扱い方法など内容が膨大になる場合は、アドバイザリー契約とは別に秘密保持契約を結ぶ企業もあります。
秘密保持契約の対象範囲・使用目的・契約違反が発生した場合の損害賠償などを必ず定義しましょう。
関連記事:【専門家監修】NDA(秘密保持契約)がM&Aにおいて果たす役割
再委託の禁止
M&A仲介会社が受託者の了解を得ずに業務を別の第三者に委託することを禁止する旨を規定します。
再委託を禁止しておかない場合、M&A仲介会社が無断で他の会社や個人に関連業務を委託するおそれがあり、最悪の場合機密情報が漏洩する可能性があります。
加えて、責任の所在が曖昧になる、安値で発注することにより業務の品質低下を起こしやすいといった問題も生じやすいです。
さらに委託者とM&A仲介会社との間に情報格差が生まれてしまい、交渉の際に不利になってしまうというデメリットもあります。
ただし、業務によっては再委任をするケースもあり、特に「デューデリジェンス(買収調査)」は仲介会社が弁護士や税理士・公認会計士などの専門家に委託することがあります。
このような場合に対応できるよう、但し書きで「委託者の承諾があれば第三者への委託が可能である」旨を明記し、委託者の同意や事前同意が必要なことを義務付けておきましょう。
関連記事:M&Aのデューデリジェンスとは?費用や期間・種類などを詳しく解説
直接交渉の禁止
多くのアドバイザリー契約には、売り手と買い手企業の直接交渉を禁止する項目が含まれます。
理由としては、M&A仲介会社が契約に基づき情報収集をして候補先を見つけたとしても、依頼者が候補先と独自に直接交渉し契約を進めてしまうと、M&A仲介会社の紹介によるM&Aといえるかどうかが曖昧となるためです。
その結果、M&A仲介会社への成功報酬に関するトラブルに発展する可能性があります。
そのため、依頼者が契約に反して直接交渉を行った場合は、M&A仲介会社が依頼者に対して損害賠償を請求できる旨を定めることができます。
アドバイザリー契約の交渉方式について
アドバイザリー契約の交渉方式には、大きく「アドバイザリー方式」と「M&A仲介方式」に分けることができます。
アドバイザリー方式
アドバイザリー方式は、売り手・買い手企業がそれぞれ異なるM&A仲介会社とアドバイザリー契約を締結します。
M&A仲介会社が契約した売り手・買い手それぞれの企業のみをサポートするため、依頼企業の利益を最大化するため力を尽くしてくれる点が、アドバイザリー方式のメリットです。
しかし、交渉過程で双方が利益を主張し合うことにもなりかねないため、交渉が長期化したり不成立になったりする可能性もあります。
アドバイザリー方式は依頼企業にとって好条件でM&Aが成立する可能性が高いことから、規模が大きい案件や上場企業のM&Aで実施されるケースが多く、特に上場企業のM&Aように株主に大きく影響を与える場合にはアドバイザリー方式が採用されるケースが多いです。
M&A仲介方式
M&A仲介方式では、売り手・買い手企業が同じM&A仲介会社とアドバイザリー契約を締結します。
同一のM&A仲介会社が中立的な立場からサポートするため、両社にとってバランスの良い結果を得られるメリットがあります。
両社のニーズを把握し交渉を進めていくM&A仲介方式では十分な話し合いが行われるため、短期間でのM&A成立を目指しやすく、企業にとっては少ない負担でM&Aを進めていける点は大きなメリットといえるでしょう。
なお、M&A仲介方式は小規模・中小企業のM&Aで採用されるケースが多いです。
アドバイザリー契約の報酬体系について
アドバイザリー契約で採用されている主な報酬体系は以下のとおりです。
- 着手金
- 中間報酬金
- 月額報酬金
- 成功報酬金
M&A仲介会社によって採用する報酬は異なるので、契約前に必ず確認しましょう。
着手金
着手金はアドバイザリー契約を締結した段階でM&A仲介会社へ支払うものです。
着手金の金額は案件の規模やM&A仲介会社の規定によって異なりますが、50万〜200万円程度が相場です。
なお、私たちM&Aベストパートナーズは「着手金無料」となっております。
中間報酬金
M&Aが進む途中で発生する費用が「中間報酬金」で、「基本合意書」の締結時に支払うのが一般的です。
中間報酬金の相場は成功報酬の10%〜20%程度、あるいは定額で設定される場合が多いです。
M&Aベストパートナーズでは、中間報酬金について250万円、もしくは成功報酬の10%に設定させていただいております。
関連記事:MOU(基本合意書)とは?契約書との違いや法的効力について解説
月額報酬金
月額報酬金は一定期間内に受ける業務に対して毎月支払う手数料のことで、リテイナーフィーと呼ばれることもあります。
月額報酬はM&A仲介会社の規定やM&Aの規模・内容によって異なり、月額20万円〜200万円程度です。
M&Aベストパートナーズは着手金・月額報酬ともに発生せず、検討ハードルを下げた報酬体系を提供させていただいております。
成功報酬金
M&Aが成約した段階で支払うのが「成功報酬金」です。
多くの場合、M&Aの取引金額に一定の報酬率を乗じる「レーマン方式」という計算方式が採用されています。
成功報酬金=報酬基準額(取引金額)✕報酬率
| 報酬基準額 | 料率 |
| 取引金額が5億円以下の部分 | 5% |
| 取引金額が5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
| 取引金額が10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
| 取引金額が50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
例)「取引金額が9億円」の場合の成功報酬金
- 5億円以下の部分:5億円✕5%=2,500万円
- 5億円〜10億円以下の場合:4億円✕4%=1,600万円
- 成功報酬金(①+②)2,500万円+1,600万円=4,100万円
なお、レーマン方式を用いる際の取引金額には以下のようなケースがありますので、契約内容には注意が必要です。
- 株式譲渡対価
- 移動総資産(株式価格+負債総額)
- 企業価値(株式価格・有利子負債)
関連記事:【早見表を掲載】レーマン方式とは?計算方法や手数料の種類を解説
アドバイザリー契約の流れ
アドバイザリー契約の契約締結から契約終了までの流れを解説するので、M&Aをスムーズに行うための参考にしてください。
関連記事:M&Aとは?M&Aの概要やメリット・デメリットなどを詳しく解説
準備期間
はじめに、M&Aの目的を明確にしましょう。
売り手企業はM&Aを行う目的や譲渡金額・譲渡タイミング・譲渡後の従業員の待遇などを明確にします。
一方の買い手企業は、M&Aで達成すべき目的やゴールを明確にした上で、M&A後の事業展開などけいえ戦略を策定しておきましょう。
買収・売却後の目的が明確になった段階で、売り手または買い手企業はM&A仲介会社に対して問い合わせや個別面談を行います。
問い合わせや個別面談の結果、信頼できるM&A仲介会社(担当者)が見つかった段階でアドバイザリー契約を締結し、M&A仲介会社による支援がスタートします。
交渉期間
依頼するM&A仲介会社が決まったら、仲介会社を通じてM&Aの条件に関する交渉を開始しましょう。
交渉期間では、売り手企業は「ノンネームシート」と呼ばれる企業名をふせた簡易の概要書を作成、相手企業へ情報を開示します。
ノンネームシートは、買い手企業が交渉の場につくか否かを検討するための重要な書面です。
買い手企業がノンネームシートの情報に魅力を感じ、売り手側も相手に興味を感じたら、経営者同士のトップ面談が行われます。
トップ面談では、これまでの情報をベースに経営方針や買収額、買収後の従業員の待遇などについて話し合いを行います。
トップ面談後に双方が納得できたら、想定される買収価格や買収の条件などの基本的な内容が記載された「基本合意書」の締結をし、最終期間へと移ります。
最終期間
基本合意書の締結後、買い手企業による売り手企業の監査「デューデリジェンス」が実施されます。
デューデリジェンスは、法務・財務・税務など多角的な視点から調査を行い、売り手企業の価値やリスクを調査する重要なプロセスです。
デューデリジェンスの結果をもとに「最終条件の調整」が行われ、M&Aの契約内容を確定する「最終契約書」を締結します。
最終契約書の締結後は株式等の引き渡しや対価の支払い、設立登記といった必要な手続き(クロージング)を行います。
アドバイザリー契約書の参考文面
アドバイザリー契約書の参考文面をご紹介します。
一般的な内また、あくまで雛形なので、最終的には法務の専門家に確認してもらうようにしましょう。
この契約書(以下「本契約」といいます)は、以下の当事者間で締結されます。
甲(委託者)
住所:
会社名:
代表者名:
乙(受託者)
住所:
会社名:
代表者名:
第1条(目的)
甲は、乙に対し、以下のアドバイザリー業務(以下「本業務」といいます)を委託し、乙はこれを受託します。
- M&Aに関する戦略的アドバイス
- 潜在的な買収・売却候補の調査・選定
- デューデリジェンスの支援
- 契約交渉の支援
- その他本業務に関連する事項
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、XXXX年XX月XX日からXXXX年XX月XX日までとします。ただし、双方が書面により合意した場合には、期間を延長することができます。
第3条(報酬)
- 甲は、乙に対し、本業務の対価として以下の報酬を支払います。
- 固定報酬:XX円(税別)
- 成功報酬:本業務の成果に基づき、別途合意する金額(税別)
- 甲は、乙に対し、毎月末日までに請求書を発行し、請求日からXX日以内に報酬を支払います。
第4条(費用負担)
- 本業務遂行に必要な交通費、宿泊費、その他の実費は甲が負担します。
- 乙は、上記実費について事前に甲の承認を得るものとします。
第5条(秘密保持)
- 乙は、本業務を遂行するにあたり知り得た甲の機密情報を第三者に漏洩してはならないものとします。
- 本契約終了後も、本条の義務は有効に存続するものとします。
第6条(契約の解除)
- 甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合、書面により通知し、相手方がXX日以内に是正しない場合には、本契約を解除することができます。
- 契約解除の際には、未払いの報酬は契約解除日からXX日以内に支払われるものとします。
第7条(不可抗力)
天災地変、戦争、テロ、労働争議、政府の行為その他の不可抗力により、本契約の履行が困難となった場合、当事者はその責任を負わないものとします。
第8条(紛争解決)
本契約に関する紛争が生じた場合、双方は誠意をもって協議し、解決を図るものとします。それでも解決しない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(その他)
本契約に定めのない事項については、双方協議の上、別途書面にて定めるものとします。
以上、本契約締結の証として、本書を二通作成し、甲乙双方が記名押印の上、各一通を保有します。
XXXX年XX月XX日
甲
住所:
会社名:
代表者名:
(印)
乙
住所:
会社名:
代表者名:
(印)
この契約書をもとに、具体的な状況や要望に応じて調整してみてください。
まとめ
アドバイザリー契約の締結は、専門的な知識による頻雑な手続きをスムーズに進めるうえで非常に重要です。
しかし、契約をするうえでアドバイザリー契約にかかる費用はもちろん、「信頼できる会社(担当者)か」や「どれほど実績があるか」をしっかり確認することが大切です。
私たちM&Aベストパートナーズは、これまでさまざまなM&Aを成功へ導いてきた豊富な実績がございます。
また、着手金及び月額報酬をゼロとすることで、M&Aに対する検討しやすい環境をご提供しております。
M&Aにおけるアドバイザリー契約をご検討の方は、まずはM&Aベストパートナーズへご相談ください。豊富な知識と経験を持つ専任アドバイザーが、目的達成に向けた最適な方法をご提案させていただきます。