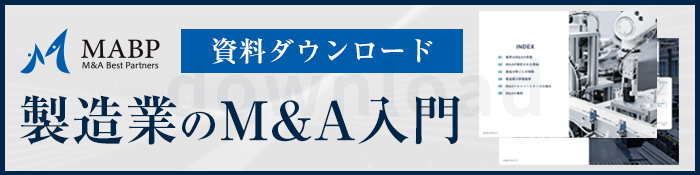化学業界のサプライチェーン(調達から消費までの流れ)には、原材料の調達や需要変動への対応のほか、国内外の拠点での製品供給や出荷の管理などさまざまな課題があります。
本記事では化学業界の現状と今後の課題について、詳しく解説します。
課題に対する解決策もご紹介するので、化学業界で課題解決にお悩みの方や、新たに参入することを検討されている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
化学業界全体の現状からみる今後の課題
化学業界全体は、どのような状況に置かれているのでしょうか。現状と今後の展望について、詳しく解説します。
製品出荷額40兆円を超える大市場
経済産業省の「科学産業の現状と課題」によると、化学製品の出荷額は2020年時点で46兆円に達しています。
製造業全体の1割強を占めており、化学業界は国内の産業全体において大きな存在となっています。
世界的に需要の増加が見込まれる
化学業界では、さまざまな技術革新の影響で、半導体などの化学製品への需要が急速に拡大しています。
特に、AI技術の発展が影響し、半導体市場の成長が著しい状況です。
また、バッテリーやICチップなど、電子機器の製造において科学製品を欠かすことはできません。日常生活で欠かすことのできない産業として、今後の需要も増加する見込みがあります。
将来的には、半導体市場がさらに拡大することが見込めます。これに伴い、化学製品の需要も増加することが予想されます。
主要な化学品の需要は海外へシフトしている
化学業界で主要な原料であるエチレンは、石油製品の基礎原料として幅広く利用されています。
しかし、バブル崩壊後の国内におけるエチレンの需要は徐々に下降してきました。これは、経済状況の変化や産業構造の転換などが大きく影響しています。
一方で、海外へのエチレン輸出量は増加しています。そのため、化学産業が今後生き残るためには海外市場の開拓がポイントです。
同時に、国内市場の再活性化に向けた施策の検討も必要です。
原油価格の高騰により大きな影響を受けている
化学業界では、主な原料として原油を使用するため、原油価格の変動は業界全体に大きな影響を及ぼします。
2020年には約20ドル/バレルだった原油価格が、2025年7月には約69ドル/バレルと、3倍以上の値上がりが起こっています。
原油価格の高騰は化学業界にとって重大な問題であり、原材料コストの上昇による収益減が懸念されます。
そのため、企業は原料の安定確保や代替品の模索、エネルギー効率の向上などの対策を検討することが必要です。
化学業界における企業の課題
化学産業に携わる企業は、社会において重要な役割を担っています。化学業界に関わる企業が解決すべき課題を解説します。
グローバル市場の獲得
化学業界は世界的な需要の増加が見込まれ、グローバル市場も大きくなっています。そのため、グローバル市場における競争力の確立は重要な課題です。
企業が国際的な市場での競争力を高めるには、製品の品質向上や技術革新、環境への配慮など、多角的な戦略の検討が必要になるでしょう。
サプライチェーン管理の最適化
化学業界では、原料メーカーと最終製品メーカーとの役割が複雑に絡み合っています。そして、原料の調達から製品の製造・流通に至るまでの連携は必要不可欠です。
しかし、サプライチェーン管理の負担は大きく、管理の効率化は急務といえるでしょう。
また、多くの化学メーカーが海外に拠点を持っているため、グローバルなサプライチェーンの構築と管理を行うことが必要です。
人手不足の解消
化学業界に限らず、日本の労働人口減少は深刻な問題となっています。少子高齢化は今後も続くことが予想されるため、労働人口問題の解消には時間がかかります。
化学業界では、技術的な専門知識や熟練した技能を持つ人材の需要が高まっています。
しかし、労働人口問題の影響で優秀な人材の供給が追いつかず、人手不足が解消されていない企業は少なくありません。
化学業界の課題に対する解決策
化学業界のが抱える課題は、状況に応じた対策を講じることで解決できる可能性があります。
課題に対する解決策をご紹介するので、対応できるものがあれば、参考にしてみてはいかがでしょうか。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の促進
化学業界が抱える課題に対処する有効な手段として、デジタル技術を駆使した業務プロセスの効率化を目指す「DXの促進」が挙げられます。
デジタル技術を活用することで研究や製造に関する生産性の向上が期待でき、効率よくコスト削減をすることができます。
さらに、AIやIoTを活用したデータ分析を行えば、製造プロセスの最適化や品質管理を向上させることもできるでしょう。その結果、無駄なリソースの削減や生産効率の向上が期待できます。
また、DXの促進には適切な人材の確保も必要です。具体的には、教育・研修プログラムの強化や業務委託の活用などが挙げられます。
M&Aの実施
M&Aによって他社の人材や技術を取り込むことで、研究開発の促進や競争力の強化が可能です。また、人材不足や後継者問題の解消といった、さまざまなメリットを得ることができます。
そのため、M&Aは化学業界において有力な選択肢であるといえるでしょう。
適切なM&A戦略の採用は、業界内でのポジションを強化したり、新たな市場へ進出したりすることが期待できます。さらに、シナジー効果によって両社の企業価値を高めることも可能です。
化学業界の課題解決につながるM&Aの事例
近年、化学業界におけるM&Aは増加傾向にあり、国内外を問わず海外企業を子会社化するケースもあります。
化学業界におけるM&Aの成功事例を2つ、ご紹介します。
A社とB社のM&A
2019年8月、A社は、トルコの樹脂コンパウンドメーカーであるB社およびその関連会社(以下Bグループ)を子会社化しました。
トルコは、欧州への輸出拠点として多くの企業が自動車や家電の生産拠点を構えており、PPコンパウンド(ポリプロピレンに柔軟性や耐熱性を与えた材料)の需要は今後も堅調な拡大が見込まれています。
A社は、Bグループの子会社化により、トルコ国内の自動車や家電メーカーへのPPコンパウンドの生産・販売力を強化しました。
C社とD社のM&A
2018年9月、C社は、アメリカの自動車内装材メーカーであるD社を子会社化しました。
C社はマテリアル、住宅、ヘルスケアの3領域で事業を展開し、石油化学製品や高機能樹脂などを製造しています。
一方で、D社は、自動車内装材の開発・製造・販売を行い、ドイツのダイムラー社やBMW社に製品を供給しています。
このM&Aにより、C社は自動車内装市場でのポジションを強化しました。
また、D社のマーケティング力やデザイン力を活かし、自動車メーカーとの強固な関係を築くことに成功しています。
まとめ
化学業界では、原材料コスト高騰の影響や競合他社との差別化が図れないことによって、収益が伸び悩む企業が増えています。
また、少子高齢化に伴い、労働人口の減少や国内市場の縮小が懸念されています。
この状況を打開するために、M&Aによって新たな技術やノウハウを取得することは有効な方法です。
多くの企業がM&Aを検討することで希望条件に合った企業が見つけやすくなり、理想的な価格でのM&Aが実現しやすくなるでしょう。
しかし、M&Aには専門的な知識がなければ、失敗するリスクがあります。
M&Aのプロである「M&Aベストパートナーズ」では、業種別に特化した専任アドバイザーがお客様のM&Aを全力でサポートします。
M&Aによって事業の継続や新たな市場の開拓を検討されている化学業界の経営者の方は、まずはM&Aベストパートナーズへお気軽にご相談ください。