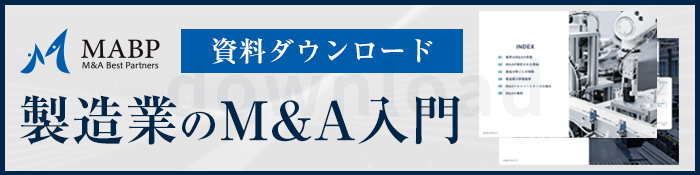人々の健康を支える安全で美味しい食品を提供するために、食品メーカーではさまざまな研究開発が行われています。
そして、競争環境の激化や後継者不足などの影響でM&Aを行う企業も見られるようになりました。
食品業界においてM&Aがどのようなメリットをもたらすのか、M&Aの専門家が詳しく解説します。
あわせてM&Aによって生じるデメリットや課題として考えられるポイントも解説するので、M&Aによって課題解決を目指そうと検討されている方はぜひ参考にしてください。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
食品業界のM&Aとは
食品業界のM&Aでは、主に原料・素材を提供するメーカーや食品加工メーカーを対象に実施されます。
原料・素材を提供しているメーカー同士、または原料・素材メーカーと食品加工メーカーがM&Aによって協力体制を構築するケースが多いです。
また、流通事業者や小売事業者といった異業種とのM&Aも見受けられます。
食品業界におけるM&Aの動向
さまざまな業種でM&Aの需要が拡大しているなかで食品業界のM&Aにはどのような傾向が見られるのか、M&Aの動向を詳しく解説します。
市場の多様性と複雑さに対応するためのM&A
時代とともに食の嗜好やトレンドは変化を続け、消費者のニーズにマッチする製品を開発できない場合、食品業界での生き残りが難しい状況です。
自社の食品製造技術やノウハウだけでは消費者が求める製品の開発が困難な場合、M&Aを行い他社と協業を目指す企業は少なくありません。
後継者不足によるM&Aの需要増
後継者問題が社会現象となっている昨今、食品業界でも重要な課題となっています。
なかでも、地元で長年にわたって経営してきた中小企業の場合は新しい人材の雇用が進まず、事業を任せられる次世代の経営陣育成が難しい企業もあります。
このような問題を解決するための手段として、M&Aによって他社に経営権を引き継ぎ、長年経営してきた会社を存続させるケースが増えています。
グローバル展開を見据えた事業拡大のためのM&A
経済のグローバル化が進んだ近年では、従来のビジネスモデルのままでは企業の存続が難しくなるケースは少なくありません。
企業が持続的な成長を続けていくためにはグローバル化に遅れないようにすることが大切なため、そのためのノウハウが豊富な企業とのM&Aを行うケースがよく見受けられます。
食品業界でM&Aを行うメリット
M&Aと聞くと、ネガティブなイメージを抱く方は少なくありませんが、実際にはさまざまな経営課題の解決につながるケースは多いです。
M&Aで得られるメリットを5つ、詳しくご紹介します。
経済的な恩恵
中小の食品メーカーの場合、全ての企業で経営基盤が盤石とは言い切れず、倒産や廃業のリスクに悩みを抱える経営者の方は少なくありません。
そのような企業がM&Aによって大手企業の傘下に入ることができれば、豊富な経営資源を活用することで経営危機を回避できる可能性があります。
また、事業そのものや株式を譲渡することで得た利益を借入金の返済に充てることができれば、個人保証からの解放も期待できるでしょう。
市場シェアの拡大
経営規模が比較的小さい食品メーカーの場合、地元では一定のシェアを確保できていても、「ほかの地域では売上が伸び悩んでいる」といったケースは多いです。
新たな地域に進出しシェアを獲得することは時間もコストもかかりますが、M&Aによって相手企業の市場を手に入れることができれば、シェア拡大の足がかりにできるでしょう。
技術・ノウハウの獲得
食品製造には高度な技術とノウハウが求められ、他社には真似できない独自の技術をもった食品メーカーも少なくありません。
しかし、消費者のニーズやトレンドに合った新製品を開発したいと考えたとき、自社の技術やノウハウだけでは実現が難しい場面もあります。
そこで、M&Aによって他社と共同開発の体制を構築することができれば、相手企業のもつ技術やノウハウを活かした質の高い製品を開発することができます。
ブランド価値の維持・向上
ブランド力や知名度の向上は、M&Aで得られる大きなメリットです。
中小企業の場合、地元では高い知名度があっても他の地域ではあまり知られていないというケースは少なくありません。
このような状況になっていると、新規エリアへの進出に苦労することも多いでしょう。
しかし、M&Aによって大手企業の傘下に入ることができれば、大手の知名度を活かした相乗効果によって自社製品やブランドの価値も高めることができるでしょう。
事業の継続
後継者不足に悩む中小企業にとって、事業の継続はもっとも重要な経営課題といえます。
M&Aによって資本力の大きいメーカーへ経営を譲渡することで、事業を継続しながら従業員の雇用も守ることができるため、経営者としての責任を最後まで果たすことができるでしょう。
食品業界でM&Aを行うデメリットと課題
食品業界でのM&Aはさまざまなメリットがありますが、その一方でデメリットや課題を把握しておくことが大切です。
M&Aを行う前に押さえておきたい重要なポイントを3つご紹介します。
統合の難しさ
食品業界に限らず、企業によって社風や文化はさまざまです。
異なる文化を持つ企業同士がM&Aを行った場合、経営統合した後に従業員同士の軋轢が生じたり、新しいやり方についていけず離職者が出てしまうことも考えられるでしょう。
最悪の場合、品質や信頼性の低下を招くことで取引先や顧客離れが生じ、経営そのものが悪化する可能性も考えられます。
このような事態を防ぐためには、M&Aを締結する前にお互いの企業文化や経営方針、将来的なビジョンなどを十分にすり合わせたうえで慎重に交渉を進めることが大切です。
法的なリスク
食品の製造にあたっては食品衛生法や食品表示保、食品安全基本法などさまざまな法律を遵守しなければなりません。
食品業界のM&Aにあたっては、相手先企業が各種法令を遵守しているかをしっかりと調査しておく必要があります。
十分な調査を行わないままM&Aを進めた結果、買収後に法令違反が発覚し、M&Aを行った結果自社のブランド力が毀損されるリスクもあります。
また、M&Aが成立した後、帳簿に記載されていない簿外債務や取引先との不利な契約などが発覚するケースもあるため、事前のデューデリジェンスで入念に法的リスクを調査しておくことが大切です。
競争環境の変化
ビジネスの世界は流動的なため、M&Aを実施することで「必ずその後の状況が必ず安定する」と約束されているわけではありません。
なかでも、食品業界はニーズの多様化やライバル企業の台頭などの影響を受けやすく、競争環境が変化しやすいです。
上記のことから、統合後にどういった経営戦略をとるのか、将来のビジョンを共有したうえでM&Aの交渉を進めていくことが重要です。
食品業界のM&Aの成功事例
食品業界内でM&Aに成功し、順調な経営を行っている企業の事例をご紹介します。
株式会社日清製粉グループ本社のM&A成功事例
小麦粉の製造・販売を中核とする株式会社日清製粉グループ本社は2022年6月、熊本製粉株式会社の発行株式のうち85%を株式譲渡によって取得しました。
日本における小麦粉市場は人口の減少や市場競争の激化によって厳しい状況となっています。
両社は、2011年より業務提携を開始して製品供給や原料調達などで協力体制を構築し、2016年の熊本地震の際には日清製品が製の代替供給や熊本製品の設備復旧支援なども行ってきました。
すでに綿密な関係を気づいてきた両社がM&Aによって一つとなることで、シナジー効果によるコスト競争力と市場への適応力の増進を図ると発表しています。
山崎製パンのM&A成功事例
2022年8月、「ランチパック」や「ダブルソフト」などで知られる山崎製パン株式会社は、包装パン事業やフレッシュベーカリー、レストラン事業を手掛ける神戸屋の事業の一部を取得しました。
事業構成の見直しを検討していた神戸屋は、フレッシュベーカリー事業・レストラン事業・冷凍パン事業に注力するために包装パン事業と子会社となっているデリカ食品事業を山崎製パンへ譲渡。
これによりう山崎製パンは神戸屋が持っていた関西地方の基盤を引き継ぎ、さらなる生産体制の強化を図っていくとしています。
株式会社ユーグレナのM&A成功事例
ユーグレナはミドリムシを原料としたサプリメントや乳酸菌飲料などを製造する健康食品メーカーです。
2005年に創業した比較的新しい企業ですが、青汁でおなじみの「キューサイ」を買収するなど10社以上の積極的なM&Aによって事業規模を拡大させてきました。
ユーグレナが創業した背景には、将来懸念されている世界的な食糧不足を解決したいという願いがあることから食用ミドリムシに着目し、世界で初めて大量培養に成功しています。
ユーグレナはSDGsというワードが一般的になる以前から「サステナブル」を大きな経営理念として掲げ、現在までその姿勢は一貫しています。
近年では食品事業に加えてコスメやスキンケアアイテム、バイオ燃料事業なども積極的に手掛けるようになり、順調に売上と利益を拡大。
創業から積極的なM&Aと研究開発、設備投資を行ってきた結果赤字が続いていましたが、2025年を目処に営業利益の連結黒字化を目標としています。
エバラ食品工業株式会社のM&A成功事例
焼肉のタレや浅漬けの素などさまざまな調味料で知られるエバラ食品工業株式会社は2023年8月、丸二株式会社(広島市)の株式を取得して子会社化しました。
1967年設立の丸二は、焼きそばソースやうどんスープといった粉末製品やお茶漬けやふりかけの原料となる顆粒製品、液体スープなどのOEM生産を主軸としている企業です。
丸二を子会社化したことで、エバラ食品工業は丸二が得意としている小容量の粉末・液体製品の製造や西日本エリアの味覚や嗜好に適した製品の開発・製造・販売を目指すとしています。
なお、エバラ食品工業は前年の2022年に液体調味料などの製造・販売を手掛けるヤマキン株式会社の子会社化も行っています。
フジッコ株式会社のM&A成功事例
昆布や豆製品、惣菜やヨーグルトなどを中心に製造・販売を手掛ける食品メーカー大手のフジッコ株式会社は、2025年7月に同社の連結子会社で中華惣菜の製造販売を行う株式会社フーズパレットを譲渡すると発表しました。
譲渡先である理想現実グループ(株式会社理想実業)傘下の株式会社プロデュースカンパニーは、理想実業が展開する飲食店「どうとんぼり神座」の食品加工を全て担っている企業です。
この譲渡により、フジッコ株式会社はコアビジネスの事業強化、中長期の収益基盤構築に向けた事業ポートフォリオの見直しを行うとしています。
まとめ
消費者のニーズが多様化し、競争が激化する食品業界で企業が生き残っていくためには、M&Aが有力な選択肢ととして挙げられます。
しかし、M&Aを実施することで必ず経営が立て直せるという保証はなく、成功させるためには将来的なビジョンや経営戦略を入念に考えたうえで経営統合を進めていくことが重要です。
私たちM&Aベストパートナーズは、M&Aのプロフェッショナルとして、これまで多くのM&Aを成功させるためのサポートをしてまいりました。
食品業界での生き残りに向けたM&Aはもちろん、後継者不足が原因で事業の継続が難しいなど、さまざまな課題を解決するための最適なご提案をさせていただきます。
M&Aによる市場拡大や事業の継続を検討されている経営者の方は、まずはお気軽にM&Aベストパートナーズにご相談ください。
専任のアドバイザーが、経営戦略実現に向けたお手伝いをさせていただきます。