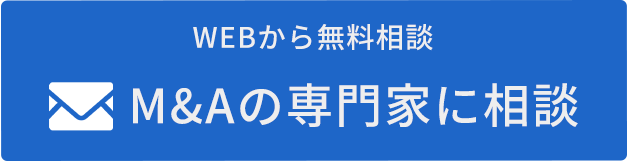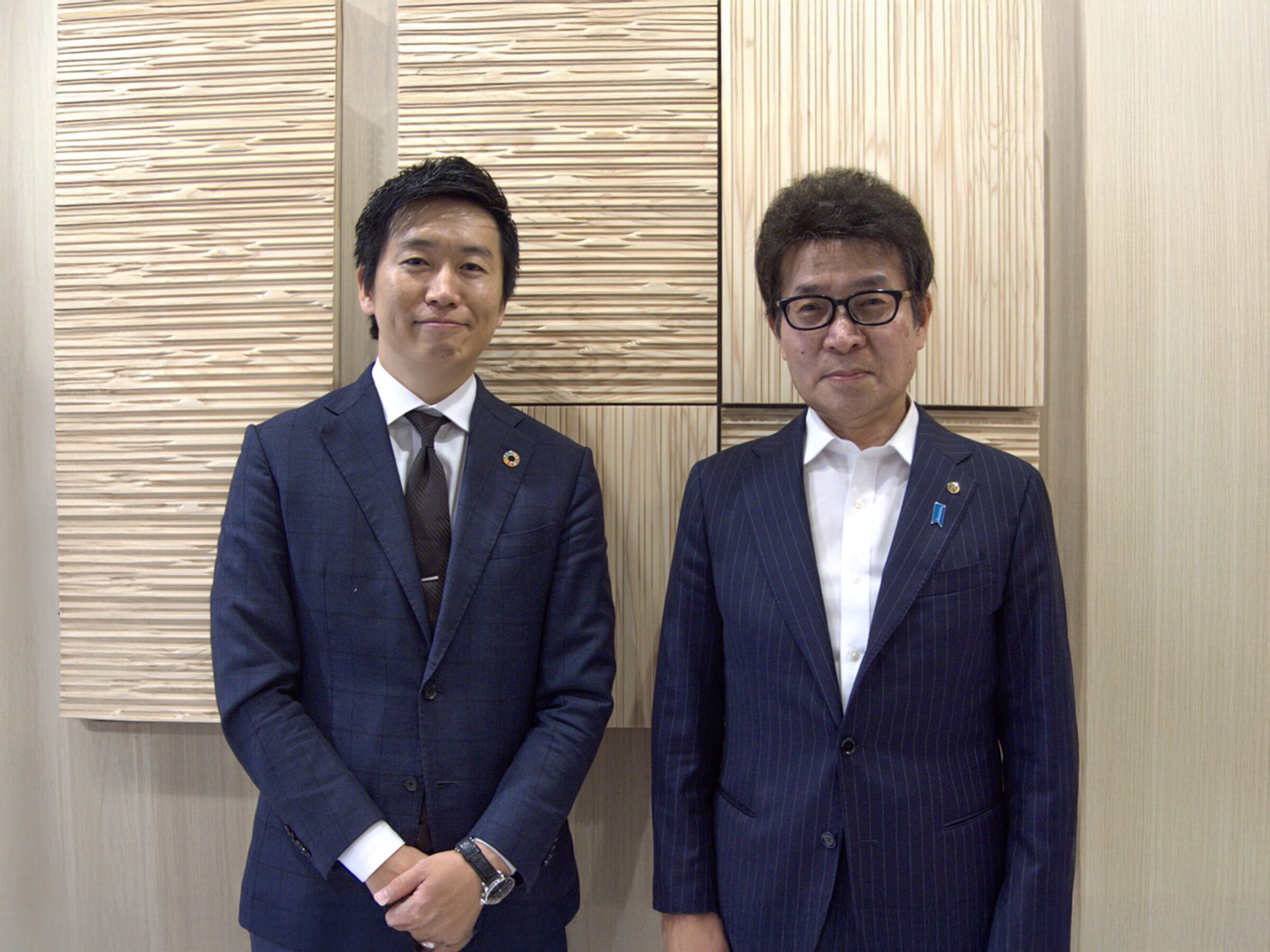化粧品の開発や製造・販売を行う化粧品業界では、さまざまな経営課題に直面する企業が多く存在します。
そのため、近年M&Aを実施するケースが増加傾向にあります。
そこで本記事では、化粧品業界におけるM&Aの動向や事例を紹介します。
また、買い手・売り手それぞれの視点から見たM&Aのメリットや成功のポイント、スキーム別のM&A事例もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:M&Aのメリット・デメリットとは?買い手・売り手側からわかりやすく解説
目次
化粧品業界におけるM&Aの動向
M&Aは業界を問わず増えていますが、各業界の構造や状況により傾向が変わってきます。
化粧品業界におけるM&Aの動向について紹介します。
M&Aによる異業種からの新規参入が増えている
M&Aには買い手・売り手の関係性が生じますが、両社の業界は異なっても実施が可能です。
なかでも化粧品業界では、異業種とのM&Aのケースが増えています。
2018年3月までの約28年程度の期間では、約110社の企業が他業種から化粧品業界へ参入しました。
また、昨今ではOEM(他社への製造委託)によって化粧品の製造を外部委託し、ネットショップの普及に伴った新規参入も増加しています。
このように、化粧品業界への参入ハードルが下がったことが、参入企業が増加した大きな要因といえるでしょう。
上記のほか、化粧品業界への参入を実現する手段としてM&Aも注目されています。
特に異業種から化粧品業界へ参入する場合、既存の化粧品会社とM&Aによって統合することで、製造設備やノウハウなどを含めて取り込むことが可能です。
そのため、今後もM&Aによる化粧品業界への参入が増えると考えられています。
海外企業とのM&Aも増加傾向にある
化粧品の国内需要は、日本の人口減少が進んでいることもあり、今後の国内需要は減少すると予測されています。
このような状況を打開することを目的とし、海外企業とM&Aを実施する日本の化粧品会社が増加しています。
日本の化粧品は海外でも評価が高く、2023年における世界の売上ランキング でも、株式会社資生堂や花王株式会社などの日本企業が上位に入っています。
海外企業によるM&Aの増加により、メイドインジャパンの信頼性ある化粧品が今後も世界へ広がっていくでしょう。
OEM企業に対するM&Aも増加傾向にある
他社から依頼を受けて化粧品を製造するOEMメーカーは、すでに化粧品事業を展開している企業、また今後新たに化粧品業界への参入を検討している異業種企業にとってもニーズが高まっています。
OEMメーカーを自社の傘下に入れることで、化粧品製造の一連のプロセスが自社で完結できることは企業にとって大きなメリットといえるでしょう。
化粧品のOEM企業を取り込み化粧品を自社製造できる体制を構築するためには、M&Aが有力な選択肢といえるでしょう。
【売り手側】M&Aで化粧品事業を売却する主なメリット
M&Aは買い手・売り手の双方にメリットがある経営戦略です。
化粧品事業を売却することで売り手側が得られる主なメリットを解説します。
ブランド力の強化を図れる
M&Aによってブランド力の高い企業の傘下に入ることができれば、ブランド力の強化を図ることが可能です。
例えば、ブランド力の高い相手企業の販売網や知名度を活用することで、自社ブランドの認知度やイメージの向上が期待できます。
また、投資家や金融機関からの評価も上がり、資金調達のハードルが下がることも期待できるでしょう。
事業承継を実現し廃業を回避できる
M&Aは、経営基盤の強化や事業拡大だけでなく「事業承継」の手段としても有効です。
化粧品業界に限らず、事業承継に頭を抱えている企業は少なくありません。
M&Aを活用することによって豊富な選択肢のなかから後継者探しができるようになり、スムーズな事業承継ができるようになるでしょう。
関連記事:M&Aで後継者問題を解決|成約事例を紹介
関連記事:「承継」と「継承」の違いとは?M&Aにおける違いを解説
従業員の確保を図れる
M&Aでは事業を承継・譲渡することで従業員の雇用を守ることもできます。
後継者問題や経営状況の悪化などが原因で廃業をした場合、これまで企業を支えてきた従業員が路頭に迷うことになってしまいます。
しかし、M&Aをすることで事業が継続できれば、従業員も同時に引き継ぐことができるため、雇用に関する不安を解決することができるでしょう。
経営者が利益を得られる可能性がある
M&Aにはさまざまなスキーム(手法)が存在します。
利益が期待できるM&Aスキームを選択することで、経営者が利益を得られる可能性があります。
例えば、株式の譲渡を通じて経営権を承継する「株式譲渡」では、売り手企業の経営者が保有する株式を買い手企業へ譲渡します。
このとき、株式取得時の金額や手数料を差し引いた金額が、売り手企業の経営者に対する利益となります。
ただし、こうした売却益には税金が生じるケースがあるため、正確に理解しておくことが大切です。
関連記事:M&Aとは?M&Aの概要やメリット・デメリットなどを詳しく解説
【買い手側】M&Aで化粧品事業を買収する主なメリット
次に、買い手となる企業がM&Aで化粧品事業を買収する主なメリットは3つ挙げられます。
短期間で化粧品事業に参入できる
化粧品業界へ新たに参入する場合、拠点の設立や人材の確保、許認可の取得といった多くのプロセスが必要です。
OEMによって製造を委託するとしても、企画や開発、販売といったプロセスは自社ですることになります。
しかし、M&Aによって化粧品事業を展開する企業を取り込むことによって、売り手企業がもつノウハウや販売網といった経営資源をそのまま引き継ぐことが可能です。
M&Aのプロセスさえ完了できれば、売り手企業の設備や人材などを活用することで短期間での参入が実現できます。
参入コストを抑えやすい
化粧品業界への新規参入は、時間だけでなく多額のコストも必要です。
設備や人材の確保、販路の開拓・許認可申請など、かかる費用はさまざまです。
しかし、すでに化粧品事業を展開している企業をM&Aにとって取り込むことで、売り手企業の持つ設備やノウハウを持った人材、販路などをそのまま活かすことができます。
新規事業に関するさまざまなコストが削減できることは、M&Aがもたらす大きなメリットといえるでしょう。
サプライチェーンの安定化が図れる
化粧品業界にはさまざまな業種があり、開発・販売をする企業やOEMによる製造を行う企業、原料を製造する企業などさまざまです。
化粧品業界のなかでも異なる役割を担っている企業同士がM&Aをすることで、開発や製造、販売といったサプライチェーンの統合・安定化が期待できます。
化粧品業界のM&A事例【M&Aスキーム別】
事業規模に関係なく、化粧品業界ではM&Aが増加傾向にあります。
そこで、化粧品業界の代表的なM&A事例について、M&Aのスキーム別にご紹介します。
株式譲渡によるM&Aの事例
2021年7月、個人や企業向けの宅配水や建築コンサルティング、子会社の株式会社JIMOSによる美容・健康事業を手掛けてきた株式会社ナックは、株式譲渡によって株式会社トレミーを子会社化しました。
トレミーはスキンケア商品を中心に化粧品や医薬品のOEM事業を展開し、企画開発から製造、許認可申請や出荷までの工程を自社で担い、JIMOSの主力製品の受託生産も行ってきた会社です。
トレミーを子会社化とすることで、ナックは既存の美容・健康分野を深化させ、また新商品開発や新規ビジネスの展開も目指します。
参考:株式会社ナック|株式会社トレミーの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
事業譲渡によるM&Aの事例
2022年、ベビー用品で知られるコンビ株式会社は、自然派化粧品ブランド「Nanarobe(ナナローブ)」の事業についてダイレクトマーケティングに強みを持ち、株式会社アイケイの子会社としてTVショッピングやECを中心に事業展開を行っている株式会社プライムダイレクトへ譲渡しました。
これにより、プライムダイレクトは強みとしているダイレクトマーケティング事業やセールスマーケティング事業の販路を活かした販売拡大を目指します。
一方で、コンビは業務提携によって譲渡した事業へ関わり、「Nanarobe」のさらなる事業成長を目指しています。
参考:コンビ株式会社|化粧品事業譲渡・業務提携に関するお知らせ
株式交換・吸収合併によるM&Aの事例
食用ミドリムシを原料としたサプリメントや乳酸菌飲料などの製造・販売で知られる株式会社ユーグレナは、2021年にサステナビリティを重視した雑貨やスキンケア商品、食品の企画開発や飲食店の運営などを手掛ける株式会社LIGUNAを株式交換いよって完全子会社化しました。
このM&AによってLIGUNAは課題となっていた後継者不足を解消し、ユーグレナはサステナビリティを主眼としたさらなる事業の拡大を目指します。
なお、ユーグレナは一層の経営強化や効率化を目的として2024年にLIGUNAを吸収合併し、その後もLIGUNAのブランドであった「akyrise」を継続しています。
参考:株式会社ユーグレナ|当社子会社との吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
化粧品業界のM&Aを成功させるためのポイント
M&Aはさまざまなメリットが見込める経営手段ですが、成功させるためにはポイントを押さえることが大切です。
化粧品業界のM&Aを成功につなげる2つのポイントを解説します。
M&Aの目的に合わせたスキームを選ぶ
M&Aにはさまざまなスキームがあり、達成できる目的も異なります。
M&Aの検討をするにあたって、まずは目的を明確にし、目的が達成できるスキームを選択することが重要です。
M&Aの検討段階で目的をはっきりさせたうえで適切な戦略を立てることで、どのスキームが適切か選ぶことができるようになるでしょう。
M&Aの専門家からアドバイスを受ける
M&Aには税務や法務といった幅広い専門知識、そしてM&Aを成功させるためのノウハウが求められます。
また、M&Aはスキームごとにさまざまなプロセスを適切に進めていかなければならず、独力でさせるいことは難しいです。
M&Aで失敗しないためにも、M&A仲介会社などの専門家とアドバイザリー契約を結び、適切なアドバイスを受けることが大切です。
まとめ
化粧品業界では、他業種からの参入や海外への進出などでM&Aが盛んに行われています。
M&Aは買い手・売り手の双方にとって多くのメリットがあるため、今後も実施する企業は増えていくと予測できます。
一方で、M&Aの実施は経営課題を解決するうえで有力ですが、成功させるためには専門家によるアドバイスが必要不可欠です。
化粧品業界におけるM&Aを検討されている方は、M&A・事業承継の実績が豊富な「M&Aベストパートナーズ」へお気軽にご相談ください。