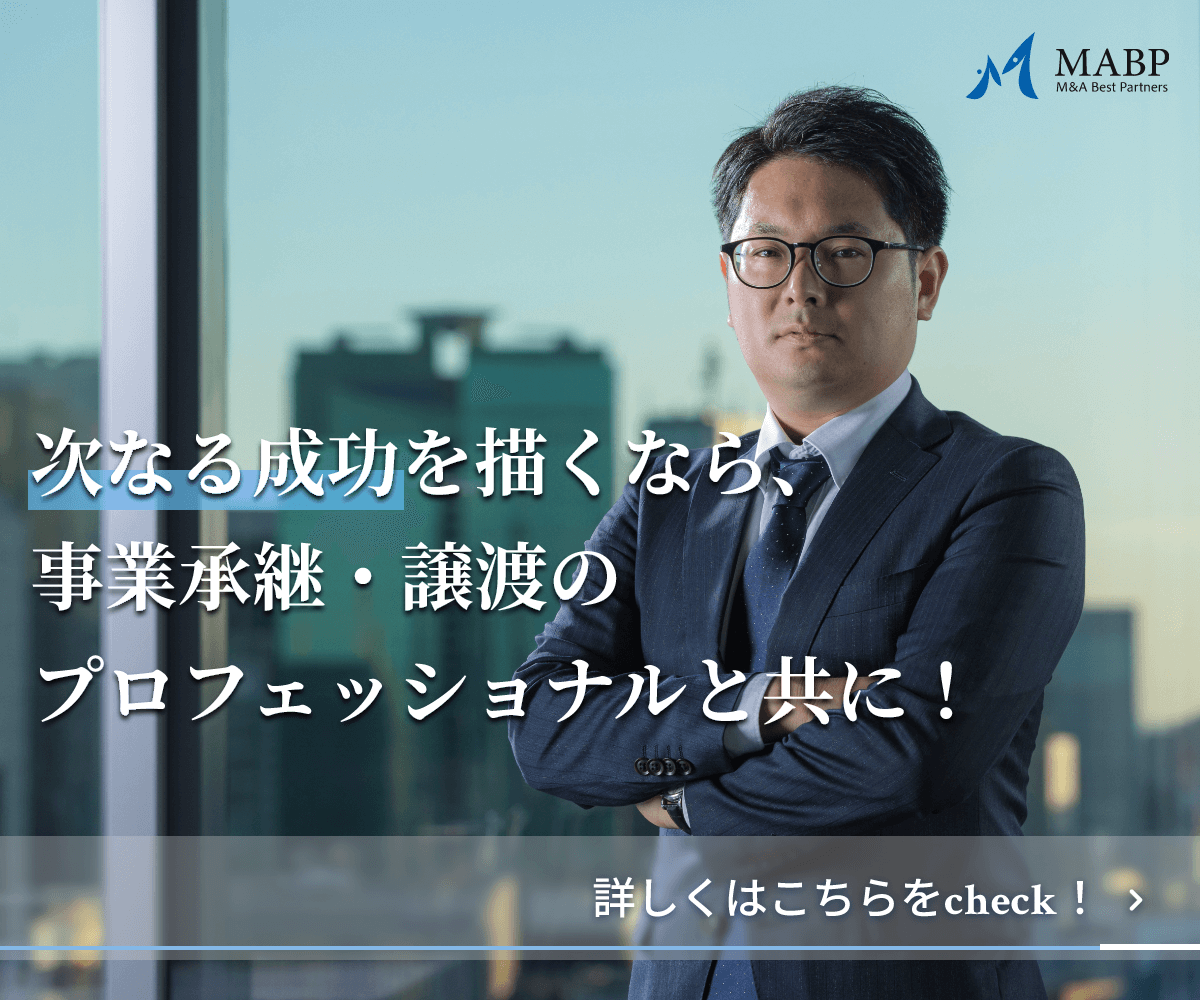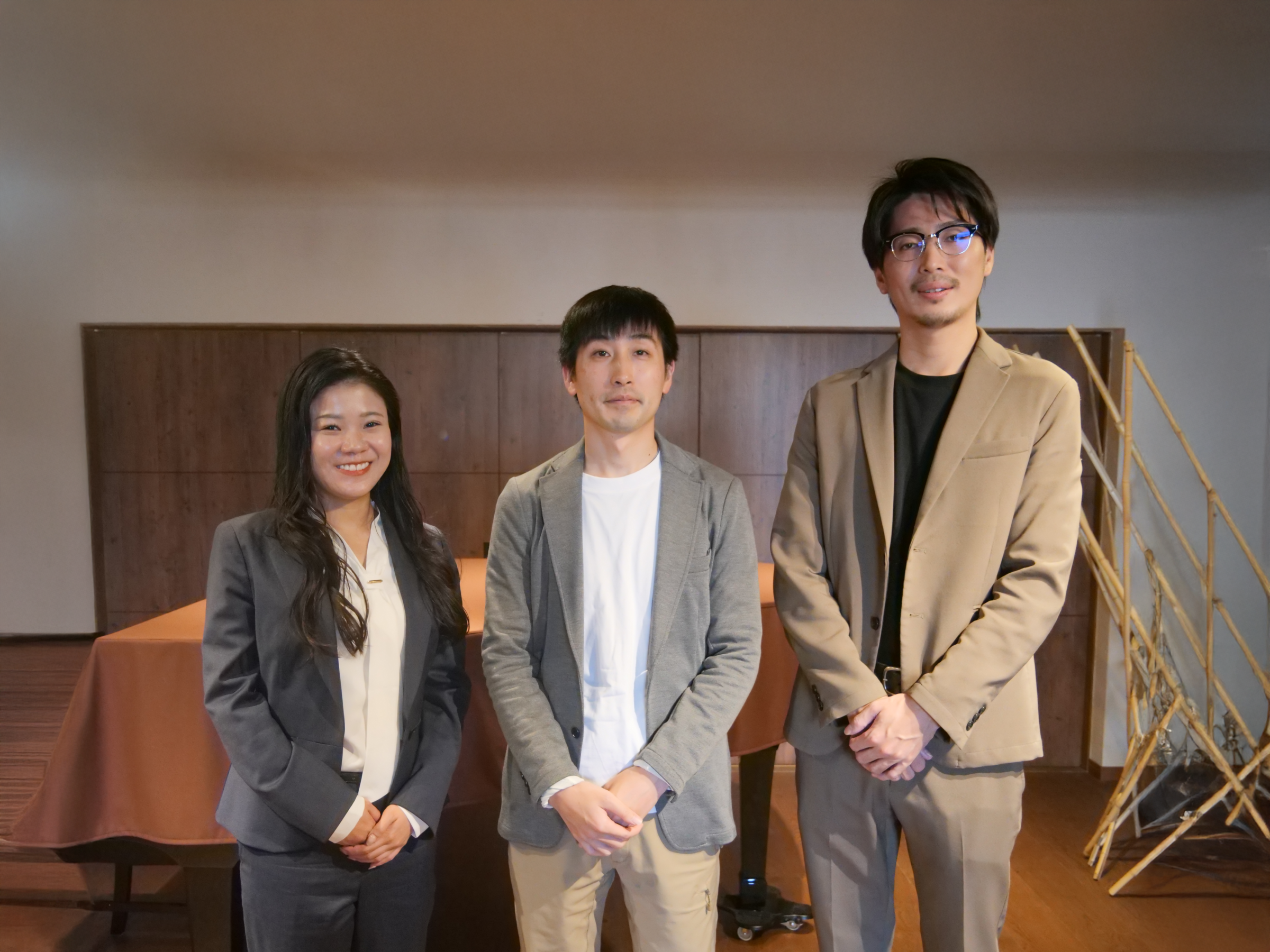「子会社化」は一般的な経営戦略であり、大企業が実施するケースも珍しくありません。
しかし、子会社はメリットが多いものの、リスクも少なからずあります。
そのため、経営者が子会社化の実施を検討するうえでは、基本事項を押さえておく必要があるでしょう。
本記事では、子会社化の基礎知識からわかりやすくお伝えします。
子会社化のメリットやリスク、成功のポイントも紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
子会社化に関する基礎知識

まずは、子会社化に関する基礎知識をお伝えします。
混同されやすい「子会社」と「関連会社」の違いについて把握しておきましょう。
子会社化とは
子会社化とは、簡単にいえば「親会社と子会社の関係を構築すること」です。
親会社は、子会社における株式の過半数を得ることで、その経営権を取得します。子会社の株主総会における意思決定では、親会社が支配的な力を持つことになるのが特徴です。
一般的に、子会社化を実施する場合は「M&A」のスキーム(手法)を用います。
M&Aとは、合併(Merger)や買収(Acquisition)を通じて複数社の統合を図る経営戦略のことです。具体的なM&Aスキームは後ほど紹介しますが、既存会社を買収して子会社にする手法や、新設会社を親会社にする手法などがあります。
子会社と関連会社(持分法適用会社)との違い
子会社と混同されやすい言葉に「関連会社」があります。
関連会社(持分法適用会社)とは、親会社に自社株を20~50%保有されている会社のことです。
一般的に「子会社」と呼ぶ場合、親会社の持株比率 (当該会社の全株式に占める株式の保有率)は過半数、つまり50%を超えています。一方で「関連会社」と呼ぶ場合、持株比率は50%を超えません。そのため、親会社は関連会社の意思決定において支配的とまではいえないものの、強い影響力は持っているといえるでしょう。
ただし、親会社が関連会社の経営を実質的に支配している場合、「子会社」と呼ぶ場合があります。これは、会社法の改正による変更点です。
対象会社によってメリットは異なる
子会社とする対象会社は、必ずしも外部の会社とは限りません。
自社の事業を子会社として独立させるケースもあります。自社の事業であっても、親会社・子会社の関係が生じるのであれば、一種の子会社化です。
子会社化のメリットは、対象会社が「外部の会社」か「自社の事業」かによって異なります。具体的なメリットは後述しますが、どちらの子会社化を実施するかで事情が変わることを把握しておきましょう。
子会社化の主な種類
子会社には、主に「完全子会社」「連結子会社」「非連結子会社」の3種類があります。
どの子会社をつくるかで、法的な扱いも異なるため注意が必要です。ここでは、それぞれについて解説します。
完全子会社
「完全子会社」とは、親会社が株式を100%保有している子会社のことです。
株主総会における議決権は、持株比率が100%である親会社が完全に握っている状態となります。議決権が分散していない分、意思決定を迅速に行えるのがメリットです。
ただし、個人や「相互会社」が株主となるケースでは、完全子会社とは呼ばれません。相互会社とは、個々の所属社員が従業員であり顧客でもある、保険業界特有の会社形態です。なお、親会社が決算を行う際には、連結決算(子会社を含めた決算)が必要となります。
連結子会社
「連結子会社」とは、親会社の持株比率が100%には満たないものの、連結決算が必要となる子会社のことです。
親会社は決算において、子会社の会計を含む「連結財務諸表」を作成する必要があります。この連結財務諸表の記載対象に含まれるのが連結子会社です。
ただし、親会社の持株比率が50%以下でも、実質的な支配関係にある場合は連結子会社と見なされる場合があります。
非連結子会社
「非連結子会社」とは、前述の連結子会社に含まれない、つまり連結決算の対象外となる子会社のことです。
親会社の持株比率が過半数であっても、特定の条件に該当することで非連結子会社と見なされる場合があります。例えば、一時的な支配関係であることが明らかなケースや、会計上の重要性が低いケースが挙げられるでしょう。
「重要性が低い」とは、売上高や資産、利益などの要素において、連結決算への影響度が著しく小さいケースを指します。
外部の会社を子会社化する親会社のメリット

親会社として子会社化の実施を考えている場合、どういったメリットが得られるのかは気になるところでしょう。
前述の通り、対象会社が「外部の会社」か「自社の事業」によって得られるメリットが異なります。
まずは、外部の会社を子会社化する4つの主なメリットについて理解しておきましょう。
事業の拡大・多角化を図れる
外部の会社を子会社化することで、親会社は事業の拡大・多角化を図れるでしょう。
外部の会社を自社の傘下に配置すれば、子会社が持つ人材や設備といった経営資源を活用できます。例えば、関東に本社を構える会社が関西の同業他社を子会社化すれば、関西での事業展開が容易となるでしょう。
子会社化では、ゼロから拠点や組織を立ち上げる必要がないため、事業戦略を早期に達成できます。
コスト削減を図れる
外部の会社を子会社化することで、コスト削減を図れます。
両社の経営資源を統合することで重複部分を共通化したり、前後のプロセスを統合したりできるためです。例えば、自動車メーカーが部品メーカーや組立メーカーを子会社化することで、自動車製造のプロセスをグループ内に集約できます。
その結果、プロセス間の連携がスムーズになり、人件費削減につながるでしょう。
経営基盤の強化を図れる
外部の会社を子会社化することで、経営基盤の強化を図れます。
資本関係にある会社が増加すると、各社の意見が分かれて経営方針の統一が難しくなるでしょう。しかし、資本関係の会社を子会社化すれば、意思決定において親会社が支配的な力を持てます。
明確な親子関係を築くことで、親会社の経営方針を各社に反映しやすくなり、円滑に経営判断を行えるでしょう。
グループとしての信頼性が高まる
外部の会社を子会社化することで、グループとしての信頼性が高まります。
親会社のブランド力を得たり、上場したりすることで、子会社の価値は高まるでしょう。
その結果、子会社を傘下に置くグループ全体の力も強まり、対外的な評価アップにつなげることが可能です。
例えば、投資家や金融機関から資金調達しやすくなる、といった効果が期待できます。
自社の事業を子会社化するメリット
続いて、自社の事業を子会社化する2つのメリットについて解説します。
外部の会社を子会社化するケースとは全く異なるため、的確に把握しておきましょう。
節税を図れる
自社の事業を子会社化することで、節税を図れます。
法人税率は、課税所得や資本金に応じて決定しますが、親会社と子会社の税率は別々に決定します。 親会社と子会社で分けることで、各社単体で見た時の課税所得が下がり、軽減税率を適用できる可能性があります。
そうなれば、最終的な法人税は下がるでしょう。ただし、法人税率は細かく改正が行われており、都道府県によって変わる場合があります。
後継者の育成を図れる
自社の事業を子会社化することで、後継者の育成を図れます。
自社から独立した子会社を設立すれば、親会社とは別の経営者を配置することが可能です。自社の有望な後継者候補を子会社に配置すれば、経営者として経験を積ませられます。
グループ全体を統括できるレベルの経営者に育てば、将来的な事業承継も可能となるでしょう。
子会社化を行う親会社のデメリット

子会社化には多くのメリットを得られますが、デメリットもあります。
子会社化を行う親会社のデメリットは、主に次の4つです。
管理の負担が増大しやすい
子会社化することで、親会社の管理の負担は増大しやすいといえます。
親会社は、子会社の業績や財務状況、従業員なども管理しなければなりません。管理対象が増える分、経理や人事の負担を抑えることは困難です。
特に、子会社化の直後は、親会社・子会社における重複部門の統合・連携などに多くのコストが生じるでしょう。
子会社の経営責任を問われる
子会社化することで、親会社が子会社の経営責任を問われる場合があります。
仮に、子会社が不祥事を起こした場合に、親会社へ経営責任が波及することを覚悟しなければなりません。別の会社であっても支配関係にある以上、親会社は子会社に対する責任を負う必要があります。
親会社はこうした事態を防ぐために、子会社に対して適切な経営上のサポートを行うことが求められるでしょう。
税金の負担が増大するケースもある
子会社化することで、親会社が支払う税金の負担が増大するケースもあります。
外部の会社を子会社化する場合は、「法人住民税の均等割」の税負担に注意が必要です。法人住民税の均等割は会社の規模に応じて税額が決まり、会社の業績が赤字であっても支払う必要があります。外部の会社を傘下に入れることでグループの規模が大きくなり、法人住民税の負担は増大するでしょう。
また、自社の事業を子会社化する場合は、「損益通算」ができないことがデメリットです。損益通算とは、赤字分を差し引くことで黒字分の課税所得を減らせる仕組みを指します。
しかし、別々の会社だと、親会社が黒字で子会社が赤字のケースでも、損益通算が行えません。その結果、前述したような節税効果を得られなくなってしまうでしょう。
取引先や従業員との関係が悪化するリスクもある
子会社化することで、取引先や従業員との関係が悪化するリスクもあります。
例えば、親会社の影響で子会社のサービス方針が変更された場合、子会社の取引先が離れてしまうかもしれません。また、親会社の企業文化が受け入れられず、従業員が離職することも考えられるでしょう。
このように、経営方針や組織体制が変更されることは、他の人に与える影響が大きいといえます。
子会社化を図る際に活用できるM&Aスキーム(手法)
冒頭でお伝えした通り、子会社化にはM&Aのスキーム(手法)を用いるのが一般的です。
ここでは、子会社化を図る際に活用できる主なM&Aスキームを3つ紹介します。
M&Aにおいてスキーム選びは重要となるため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
株式譲渡
「株式譲渡」は、売り手が保有する株式を買い手に譲渡することで、経営権を承継するM&Aスキームです。
親会社は、対象会社が保有する株式の過半数を取得することで、子会社化できます。
株式譲渡を実施する場合、株式以外の資産や権利を1つずつ移転させる必要がありません。そのため、手続きがシンプルなことが強みであるため、M&Aスキームのなかで最も一般的な手法といえるでしょう。
ただし、買い手は資産だけでなく負債を売り手から引き継いでしまうリスクもあるので、細かな事前調査が必要です。
株式交換
「株式交換」は、買い手と売り手が株式を交換することで、親子関係を構築するM&Aスキームです。
買い手は売り手の全株式を取得し、売り手の株主は対価として買い手の株式を受け取ります。なお、売り手の株主は金銭を受け取ることも可能です。
株式交換は、対象会社の株式を100%取得して完全子会社にします。買い手は新しく発行した株式を対価にできるため、資金調達の手間を省力化できるのがメリットです。一方で、株式の大々的な移転が生じるため、既存の株主から理解を得にくい側面もあります。
株式移転
「株式移転」は、新設した親会社に全株式を移転することで、親子関係を構築するM&Aスキームです。
株式の移転元となる会社は、株式交換と同様に完全子会社となります。子会社の株主は、対価として親会社から株式や金銭を受け取ることが可能です。
新株を対価にできる、株主から理解を得にくい、といった点は株式交換と共通しています。なお、株式移転は、持株会社(ホールディングカンパニー)の設立時に採用されることが一般的です。
子会社化を成功につなげるポイント

前述した通り、子会社化を行えば多くのメリットを得られますが、リスクも存在します。
そのため、正しく実施できないと、失敗につながる可能性もあるでしょう。
以下では、子会社化を成功につなげるポイントを3つ紹介します。
ステークホルダーからの理解を得る
子会社化は、取引先や従業員といったステークホルダーへ大きな影響を与える可能性があります。
ステークホルダーとの関係悪化を防ぐには、事前に理解を得ることが大切です。
具体的には、子会社化の目的や戦略、ステークホルダーへの影響などについて説明しましょう。
ステークホルダーから反対意見があれば耳を傾け、子会社化の戦略を調整することも必要です。
対象会社のリスクを精査する
外部の会社を子会社化する場合は、対象会社のリスクを精査しましょう。
株式譲渡のようなM&Aスキームでは、子会社の負債を受け継いでしまうリスクもあります。
こうした事態を防ぐために、子会社化の実施前にリスクを検出しておくことが重要です。
具体的には、隠れ債務や税金滞納などの問題がないか確認し、本当に子会社化を実施すべきか判断しましょう。
不安があれば専門家の力を借りる
自社だけで子会社化を進めることに不安があれば、M&Aの専門家から力を借りましょう。
子会社化はM&Aの一種であり、多くのプロセスを長期にわたり進めていく必要があります。さまざまな専門知識が要求されるため、経験のない経営者が適切にプロセスを進めることは容易ではありません。
M&Aの経験・知識が豊富な専門家であれば、子会社化の成功につながる適切なアドバイスを提供してくれます。
子会社化で失敗しないためにも、M&Aの専門家に依頼することを検討しましょう。
まとめ
外部の会社を子会社化する場合には、事業の拡大・多角化を図れる、コスト削減を図れるなどのメリットを得られます。
一方で、自社の事業を子会社化する場合には、節税を図れる、後継者の育成を図れるなどのメリットを得られるでしょう。
ただし、子会社化の実現にはリスクを伴います。子会社化に用いるM&Aのプロセスを正しく進められないと、失敗につながる可能性もあるでしょう。
子会社化を自社だけで進められるか不安であれば、M&A・事業継承の実績が豊富な「M&Aベストパートナーズ」へお気軽にご相談ください。