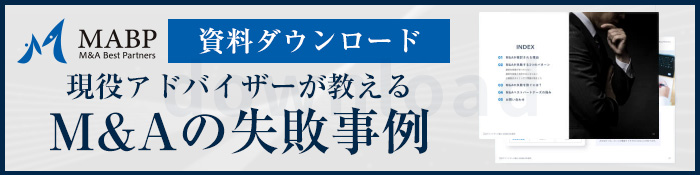この記事に辿り着いた方の中には、事業の譲渡や売却をご検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
何らかの理由で事業を継続できなくなった時、未来へ夢を託す選択肢の一つとなるのが事業承継です。
しかし、事業承継は経営者だけの都合ではなく、関係する各所とのすり合わせや、金融・法律関係の複雑な事業が絡んできます。
当然、その中でトラブルが起きてしまうことも。本記事では、事業承継で実際に起こったトラブルをもとに、回避策や実際に起こった際の対応について、M&A仲介のプロが解説します。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
事業承継で起こり得るトラブルの種類とその原因
経営者の高齢化が進む日本において、事業承継を検討する企業も増えてきました。
しかし、数ヶ月から長くて1年以上を超える期間をかけて進めていく事業承継のプロセスにおいて、何らかのトラブルが発生することは決して珍しくありません。
事業承継で発生するトラブルはさまざまな理由が考えられますが、いくつかの原因に大別することができます。
ここでは事業承継で起こりがちな以下のトラブルとその原因を解説します。
- 親族間のトラブル
- 後継者の能力不足・選定ミス
- 社内の反発(従業員・役員とのトラブル)
- 外部ステークホルダー(取引先・金融機関)との関係悪化
- 税務・財務面でのトラブル
- 事業承継の計画が不十分なことによる混乱
- 法律・契約関連のトラブル
親族間のトラブル
会社や事業を息子やその他の親族に引き継ぐ上で、考え方や価値観の違いが原因でトラブルに発展することがあります。
具体的には「長男が継ぐのが当然」という意見がある一方で「兄弟で会社を分けるべきだ」とする反対意見が出るなど、候補者が複数いる場合に誰が継ぐかで対立することは多いです。
また、株式や相続の分配において「会社を継がない親族にも相続させるべきか」などで意見が分かれてトラブルに発展する場合もあります。この場合、株が分散することで経営権が不安定になるリスクも孕んでいます。
特に遺言書がないといった場合はこうした親族間でのトラブルになる可能性が高いため、意向を明確にしておくようにしましょう。
後継者の能力不足・選定ミス
引き継ぎが完了した後の話になりますが、後継者のリーダーシップや経営の経験が足りず業績が悪化し、結果的に失敗してしまうというトラブルにつながります。
また、先代がワンマンのカリスマ経営者だった場合、後継者が組織をまとめられないといったケースも。
社内外からの支持を得られないと事業承継を成功に導くのは困難であるため、「安心して全て任せられる!」と自信を持って言える後継者を選ぶ必要があるでしょう。
社内の反発(従業員・役員とのトラブル)
「新しい社長に信頼がない」「待遇が悪化しそう」といった不安から、従業員のモチベーション低下を招く可能性があります。
また、役員との意見の対立が起こる場合があり、旧経営陣と新社長の間で意見が合わず、経営方針を巡って混乱が生じることも。
そして最も気を付けなければならないのが、先代経営者が実質的な影響力を持ち続けてしまい、新社長が意思決定できないことです。
外部ステークホルダー(取引先・金融機関)との関係悪化
取引先や銀行に「新経営者の手腕が未知数」として警戒されてしまうことも、事業承継が滞るよくありがちなトラブルです。
「今後の経営が不透明」という理由から取引条件を厳しくされたり、融資を渋られるといった事態が考えられます。
また、先代がカリスマ経営者で、会社というより個人的な繋がりが強かった場合、「先代がいなくなったら取引を見直したい」となるケースもあります。
税務・財務面でのトラブル
事業承継では大きな金額が動くため、通常であれば高額な税金が発生することに。
これに対応するために「事業承継税制」という、簡単に言えば贈与税や相続税の納税を猶予する制度があります。
とはいえ、これは放っておけば勝手に適用されるというものではなく、適切な手順を踏まなければ利用できない制度です。
また、会社の資産や負債を整理できておらず、引き継いだ後に問題が発覚することもあります。財務に関する状況を完璧に把握して事業承継に臨む必要があるでしょう。
事業承継の計画が不十分なことによる混乱
しかし、突発的な発想でろくに準備もせず事業承継を行おうとして、事業承継そのものが上手く進まないだけならまだしも、社内外に混乱が生じる場合も。
景気が悪いタイミングで事業承継を実施してしまい、立て直しに苦労するといったことも考えられます。
後進に引き継ぐ責任として、自身が経営者を退いた後も、事業がしっかりと存続できるよう計画を立てて事業承継を行うことが必要です。
法律・契約関連のトラブル
1件の事業承継を進めるうえで、さまざまな契約事項が発生します。
事業承継においては契約書全てデジタル化されているわけではないため、紙の契約書に署名やサインを求められることも多いでしょう。
それらの不備が生じてしまうと事業承継が滞る原因となります。
重要な商標や特許の権利が適切に承継されないということになれば、会社としても大きな損失になってしまいます。
労働契約関係の不備があると後継者に労務トラブルを引き継ぐリスクとなるため、法律・契約関連の対応は適切に行うことが求められます。
事業承継で実際に起こったトラブル事例
ここでは、社名を伏せる形で実際に起こった事業承継トラブルの事例を紹介し、そこから得られる教訓を見ていきましょう。
事例1:親族間の対立で会社が分裂
【背景】
- 創業者が急逝し、長男と次男の間で後継者争いが勃発。
- 創業者は長男を後継者として考えていたものの、正式な遺言を残していなかった。
- 次男は「自分も会社経営に関わってきたから後継者となる権利があるはず」と主張し、経営権をめぐって対立が深まることに。
【結果】
- 兄弟間の話し合いが決裂し、次男が社内の一部社員を引き連れて独立。
- 会社は事業の一部を失い業績が悪化。
- 後継者争いの影響で主要取引先が不安を抱き、一部契約を見直す事態に。
【教訓】
- 遺言や事前の合意形成をしておくことで後継者争いを防ぐ
- 兄弟や親族間で事業承継の方針を早めに共有し、対話の場を設けることが重要
事例2:後継者の能力不足で業績悪化
【背景】
- 60年以上続く老舗製造業の社長が健康を理由に引退し、息子に経営を引き継ぐ。
- 息子は大学卒業後すぐに社長に就任し、経営経験がほぼゼロ。
- 社内の管理体制や財務状況を把握しきれず、社員からの信頼も得られなかった。
【結果】
- 社内の混乱が続き、古参社員の大量退職が発生。
- 経営不振で資金繰りが悪化し、銀行からの追加融資も断られる。
- 事業縮小を余儀なくされ、最終的に他社へ吸収合併される形で存続。
【教訓】
- 後継者は計画的に育成し、経営スキルを磨かせる。
- いきなり社長にするのではなく、徐々に業務を引き継ぐ段階的な承継を検討する。
事例3:社員の反発により社内に混乱が発生
【背景】
- 創業者が退任し、外部から新社長を招聘(非親族承継)。
- 新社長は前職の経験を活かし、経営改革を推進。
- しかし、長年の社員との関係を築くことなく改革を進めたため、従業員の反発を招く。
【結果】
- ベテラン社員の大量退職が発生し、社内のノウハウが流出。
- 新経営陣と従業員の間に溝ができ、社内の雰囲気が悪化。
- 結果的に新社長は1年で辞任し、再び経営体制が変更される混乱が発生。
【教訓】
- 社内の信頼関係を築くため、従業員とコミュニケーションを十分に取る。
- 事業承継後の変革は段階的に進め、従業員の意見を取り入れる。
事例4:株式の分配ミスで経営権が揺らぐ
【背景】
- 先代社長が「親族全員で会社を支えるべき」と考え、複数の親族に株式を分配。
- しかし、経営に関わらない親族も株式を保有し、配当だけを期待する状態に。
- 会社の方針を決める際に、経営方針を巡って対立が発生。
【結果】
- 後継者が自由に経営判断を下せず、意思決定が遅れる。
- 株式を持つ親族が「経営方針が気に入らない」として、外部企業への売却を検討。
- 結果的に株式の買い戻しに多額の資金が必要となり、経営の負担が増大。
【教訓】
- 経営に関与しない親族に安易に株式を分配しない。
- 事業承継前に「株主間契約」や「株式譲渡のルール」を明確にする。
事例5:取引先の信用低下により契約打ち切り
【背景】
- 30年以上続くBtoB企業で、社長が健康上の理由で引退し、息子が社長に就任。
- 取引先との関係は先代社長の人脈によるものが多く、新社長は関係をうまく引き継げなかった。
- 取引先が「新経営陣が信頼できるか不透明」と感じ、契約の見直しを進める。
【結果】
- 主要取引先が契約を更新せず、売上が急減。
- 取引条件の見直しを求められ、利益率が大幅に低下。
- 最終的に別の企業との提携により業績を持ち直すが、大きな痛手を受ける。
【教訓】
- 事業承継の際は、取引先との関係を計画的に引き継ぐ。
- 新社長は就任前から取引先とコミュニケーションを取り、信頼を築く。
事例6:事業承継税制を活用せず、多額の税負担が発生
【背景】
- 中小企業の社長が事業承継を決意するも、事業承継税制の活用を検討せず、株式を贈与。
- その結果、後継者である息子に多額の相続税・贈与税の負担が発生。
- 会社の利益だけでは支払えず、金融機関からの借入が必要になった。
【結果】
- 財務負担が増大し、投資や事業拡大に支障をきたす。
- 事業承継後すぐに財務状況が悪化し、資金繰りが逼迫。
- 最終的に税理士と相談し、他の資産売却などで対応。
【教訓】
- 事業承継税制を活用し、税負担を軽減する計画を立てる。
- 事業承継の際は、税務・財務面の専門家のアドバイスを受ける。
事業承継のトラブルが発生しないようにするには
事業承継ではさまざまな原因とシチュエーションでトラブルが発生するということが分かってきたところで、そうした事態を防ぐためにできる対策をご紹介します。
早期に事業承継計画を立てる
事業承継に向けた準備は数年単位をかけて行うことが推奨されます。理想を言えば5〜10年前から始めておくと、トラブルが発生するリスクを大きく軽減できるでしょう。
【ポイント】
- 計画が遅れると、後継者の育成や財務・税務対策が不十分になる
- 「まだ先のこと」と思わず、段階的に進めることが重要
事業承継計画の立て方は下記を参考にしてみてください。
- 現状分析:自社の経営状況・財務状態・資産(株式)の分布を確認
- 後継者の選定:親族内か、社内昇格か、M&Aかを決定
- 後継者の育成:必要な知識・経験を積ませる
- 税務・財務対策:相続税・贈与税の負担を軽減する
- 利害関係者(社員・取引先・金融機関)との調整:事前に承継計画を共有し、信頼関係を築く
後継者を慎重に選び育成する
事業承継では後継者選びのミスが最大のトラブルの原因になります。以下のポイントを基準に選定しましょう。
【後継者選びのチェックポイント】
- 経営者としての資質があるか(リーダーシップ・決断力・ビジョン)
- 社内外の信頼を得られる人物か(従業員や取引先からの支持)
- 必要なスキル・経験を持っているか(財務・経営戦略の知識)
【選択肢の比較】
| 承継パターン | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 親族内承継 | 経営理念を継承しやすい | 適性がないと企業が傾く |
| 社内承継 | 社内事情を理解している | 親族の反発がある場合も |
| 外部招聘 | 専門的な経営スキルを持つ | 企業文化に適応できないリスク |
| M&A | 後継者問題を解決できる | 企業の独立性が失われる可能性 |
後継者の能力によりますが、基本的にはいきなり全権を委譲せず、少しずつ実務を担当させていくことが重要です。
株式・相続のトラブルを防ぐ
まずは、以下のポイントをおさえて株式の分散を防ぐことが重要です。
- 経営権を維持するため、株式を1人(または経営に関与する者)に集中させる
- 遺言書を作成し、「誰がどの割合で株式を持つか」を明確にする
- 経営に関与しない親族に株を持たせる場合、配当のルールを定める
また、次の点を意識して株主間契約を結ぶようにしましょう。
- 承継後の経営方針を共有し、合意を取る
- 勝手に株を売却できないルール(譲渡制限)を設定
- 株式買取の優先権を設定(会社が先に買い戻せるようにする)
税務・財務の準備を徹底する
事業承継で得られる利益を最大化するために事業承継税制を活用しましょう。
【ポイント】
- 事業承継時の相続税・贈与税を軽減できる「事業承継税制」を活用
- 要件を満たせば、最大100%の税負担を猶予・免除可能
- 専門家(税理士・会計士)と相談しながら活用を検討
また、財務状況を適切に整理しておくことも重要です。
- 会社の資産・負債をリスト化し、後継者に説明
- キャッシュフローを見直し、経営基盤を安定させる
- 不要な資産や負債を整理し、引き継ぎ後の負担を減らす
従業員・取引先とのコミュニケーションを十分にとっておく
事業承継を行うということは、その会社を取り巻く全ての人間に多少なりとも影響を与えることになります。そのため社内外で信頼関係を築いておきましょう。
- 突然の交代は社内の不安を招くため、事前に承継計画を発表
- 従業員向けの説明会を開催し、今後の方針を明確に伝える
- 取引先や金融機関に後継者を紹介し、関係を強化
先代が影響を残しすぎると新社長の権威が損なわれるため、旧経営者はあくまで“アドバイザー”の立場にとどまり、口出ししすぎないことが重要です。
法務・契約の整備
事業承継に関する契約書を適切に管理しておけなければ、思わぬところで躓く要因となってしまいます。特に以下のポイントをおさえておきましょう。
- 事業譲渡契約(事業の資産・負債の引き継ぎルールを明文化)
- 株主間契約(株式の売却ルールを明確化)
- 雇用契約の見直し(後継者がスムーズに経営できる環境を作る)
会社の営業許可や特許・商標といった知的財産が適切に引き継がれているかを確認するようにしましょう。
専門家のサポートを活用
事業承継は専門的な知識が必要なため、弁護士・税理士・会計士・コンサルタントの支援を受けながら進めていきましょう。
【事業承継に関わる各分野の専門家】
| 専門家 | 役割 |
|---|---|
| 税理士・会計士 | 相続税・贈与税対策、財務の健全化 |
| 弁護士 | 遺言書作成、株主間契約、法的トラブル回避 |
| 事業承継コンサルタント | 承継計画の立案、全体管理 |
| 金融機関 | 事業承継融資、資金調達支援 |
事業承継でトラブルが発生してしまったら?
事業承継は経営者一人の力で進めていくことはできません。そのため、どれだけ気を付けてもトラブルが発生するリスクをゼロにすることはできないでしょう。
万が一事業承継でトラブルが起こってしまった場合の対処について解説します。
まずは現状の把握と問題の整理から
まずは事実関係を正確に把握することから始めましょう。問題の大元を見誤った対応をしてしまうと、その後に新たな問題が発生する可能性があります。
ポイントは下記のとおりです。
- 何が問題なのか、関係者の意見や主張を整理する
- トラブルの発生原因(株式、相続、後継者争い、財務問題など)を特定する
- 社内外の関係者(役員、従業員、取引先、金融機関)にどのような影響が出ているかを確認する
問題を把握したら関係者との話し合いを行います。その際は感情的にならず、客観的なデータをもとに冷静に話し合うことで迅速な問題解決につながります。
必要に応じて問題が発生した分野の専門家を交えて協議しましょう。
トラブルの種類ごとの具体的な対処法
ここではトラブルの種類ごとに、NGとなる対応と適切な対応をご紹介します。
ケース1:親族間で後継者争いが発生
【対応策】
- 弁護士や第三者の専門家を介入させ、冷静な判断を促す
- 家族会議を開き、親族全員が納得できる形で合意形成を図る
- 遺言書や株主総会の決議など、法的な証拠を整理し、円満な解決を目指す
【具体例】
- NG対応:親族間で感情的に対立し、話し合いが進まない
- 適切な対応:弁護士や事業承継コンサルタントを交えた家族会議で話し合いを進める
ケース2:後継者の経営能力不足により業績が悪化
【対応策】
- 社外の経営アドバイザーを活用し、経営指導を受ける
- 必要に応じて経営体制を見直し、補佐役を配置する
- 現経営者が一時的に復帰し、後継者を再教育する
【具体例】
- NG対応:無策のまま業績悪化を放置し、社員の不安を高める
- 適切な対応:社外の専門家を入れ、後継者の育成を強化する
ケース3:社員や役員の反発が発生
【対応策】
- 新経営者が従業員と積極的にコミュニケーションをとる
- 経営方針を明確にし、従業員の不安を解消するための説明会を開く
- 旧経営者が信頼関係の橋渡し役となり、社員の理解を得る
【具体例】
- NG対応:強引な改革を進め、ベテラン社員の大量退職を招く
- 適切な対応:対話の場を設け、従業員の意見を尊重しながら方針を決定する
ケース4:取引先や金融機関との関係が悪化
【対応策】
- 早急に取引先・金融機関と面談し、経営方針を説明する
- 新経営者のビジョンを明確に伝え、信頼関係の再構築を図る
- 必要に応じて旧経営者が同行し、信用補完を行う
【具体例】
- NG対応:取引先との関係が悪化したまま放置し、契約打ち切りが続出する
- 適切な対応:新経営者が積極的に取引先と対話し、信用回復に努める
ケース5:株式や相続に関する法的トラブル
【対応策】
- 弁護士や税理士と相談し、適切な法的手続きを進める
- 遺言書や株主間契約がある場合は、それをもとに解決を図る
- 株式の買取や持ち分調整を行い、経営の安定を確保する
【具体例】
- NG対応:親族間の株式争いが激化し、訴訟に発展する
- 適切な対応:弁護士を交え、話し合いによる解決を目指す
ケース6:財務・税務の問題が発覚
【対応策】
- 事業承継税制を活用し、税負担の軽減を図る
- 資金繰り計画を見直し、必要なら金融機関と融資交渉を行う
- 経営改善のためにコスト削減や事業の見直しを実施する
【具体例】
- NG対応:相続税の支払いで資金繰りが悪化し、経営が立ち行かなくなる
- 適切な対応:税理士と相談し、分割納税や税制優遇を活用する
早急にM&A仲介に相談するという手段も
事業承継のトラブルは、専門家のサポートを受けることでスムーズに解決できるケースが多いです。
税務、財務、法律、契約、金融などさまざまな障壁があり、それぞれの専門家に相談するのがベストですが、これらが複雑に絡み合ってしまっている場合もあるので、困ったら事業承継全体の専門家であるM&A仲介業者に相談するのが良いでしょう。
事業承継のトラブルに関するご相談ならM&Aベストパートナーズまで
私たちM&Aベストパートナーズは建設・製造・不動産・医療・ヘルスケア・物流・IT業界に特化したM&A仲介会社であり、これまで多数の仲介実績があります。
また、より多くのお客様にご検討いただくため、着手金なしで仲介を承っております。
上記以外にもさまざまな案件に対応可能ですので、事業承継におけるトラブルでお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。
まとめ
事業承継は長い期間をかけて進めていくことになるため、その道中でトラブルが起きることは決して珍しくありません。
トラブルの原因で多いのが、後継者候補や従業員、既存の取引先など、関係各所との人間関係的なもの。
次に多いのが、財務・税務・法律などの複雑な手続きで不備が生じてしまうことです。
こうしたトラブルの原因が起きないように、相談役となるのが事業承継のエキスパートであるM&A仲介です。
事業承継をご検討されている方は、ぜひM&Aベストパートナーズまでご相談ください。