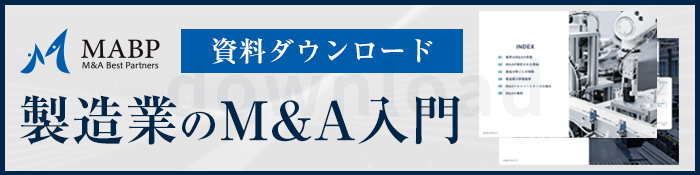昨今の自動車業界ではEVや自動運転などが大きなトピックスとして注目されており、100年に一度ともよばれる大変革期が到来しています。
これまでと同様のビジネスモデルが通用するとは限らず、企業が生き残っていくためには将来を見据えた経営の舵取りが求められます。
そこで注目されているのが、M&Aによる経営再建や事業規模の拡大です。本記事では自動車業界におけるM&Aの最新動向と事例をご紹介します。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
自動車業界全般におけるM&Aの概要
日本において自動車産業は経済活動を支える基幹産業のひとつに位置づけられており、名目GDPは13.9兆円、全産業の中で2.5%もの割合を占めています。
トヨタや日産、ホンダといった世界的にも一定のシェアを誇る自動車メーカーを擁しているほか、自動車の製造に欠かせない部品メーカーも数多く存在します。
また、自動車業界の裾野は広く、自動車製造だけでなく整備を担う企業や小売業者であるディーラーなども含まれます。
これまでの歴史を振り返ってみると、高度経済成長期を経て日本が戦後からの経済復興を果たしたのは、自動車産業が大きく貢献していることは間違いないでしょう。
しかし、近年の自動車業界は100年に一度ともよばれる大変革期を迎えており、EV(電気自動車)や自動運転技術をはじめとした開発競争が激化しています。
自動車=エンジンを動力とした乗り物、あるいは人間が運転する乗り物、といった従来の概念が根底から覆され、新たな技術に対応できないメーカーは今後淘汰されていく可能性もあるでしょう。
自動車メーカーがこれまで蓄積してきた技術力やノウハウだけでは対応できないことも多いため、さまざまな企業とM&Aを行うケースが増えています。
自動車部品業界のM&Aの動向
ここからは、自動車産業を支えるさまざまな業界ごとにどういった再編が進んでいるのか、M&Aの最新動向を解説します。
まず初めに、自動車の製造に欠かせない部品業界の動向からご紹介します。
2000年代以降の自動車部品業界を振り返ってみると、リーマンショックや東日本大震災、コロナ禍などの危機に見舞われ、自動車部品業界は一時的に販売が落ち込んだことがありました。
現在では業界全体の売上も回復し順調な経営を続けているメーカーが多いですが、今後はEVや自動運転といった新たなニーズに対応できるかが重要なポイントとなります。
現在の自動車は従来の製品に比べて電子部品の数が増えており、EVや自動運転が実用化されれば部品はさらに複雑化していくでしょう。
そのため、自動車部品メーカーの中には、このような将来を見越して電子部品メーカーや電子機器メーカーとM&Aを行うケースが増えつつあります。
また、自動車部品業界には、優れた技術力をもっているものの人手不足に頭を悩ませている企業や、経営を引き継ぐ後継者が不在という企業も少なくありません。
そこで、小規模事業者を中心に大手メーカーの傘下に入り人手の確保や経営の安定化を図るケースもあります。
自動車ディーラー業界のM&Aの動向
自動車ディーラーとは、特定の自動車メーカーと特約店契約を結んでいる小売事業者のことです。
一般的にディーラーは新車をメインで取り扱っている販売店というイメージがありますが、中古車販売や自動車部品およびオプションパーツの販売、整備なども大きな収益の柱となっています。
日本国内における自動車ディーラー業界の市場規模は、2000年代以降毎年15兆円から18兆円前後で推移しています。
少子高齢化や人口減少が続く日本において、自動車販売の市場規模や販売台数が劇的に増加するとは考えにくく、今後も横ばい状態または減少に転じる可能性が高いといえるでしょう。
また、今後さらにカーシェアリングが普及した場合、自動車を所有するユーザーは減り続けるとも予想されます。
このような状況もあり、自動車ディーラーは将来を見据えた経営の効率化や経営基盤の強化が求められます。
そこで、特に経営規模の小さい自動車ディーラーはM&Aによって大手ディーラーと手を組むケースが増えており、今後さらに業界再編が進んでいくと予想されます。
自動車整備業界のM&Aの動向
自動車は車両を購入して終わりではなく、車検や各種整備、メンテナンスなども必要です。
これらを担うのが自動車整備業界であり、全国にチェーン展開している自動車整備会社から地元で長年にわたって経営している整備業者まで数多くの事業者があります。
一口に自動車整備といってもそのジャンルは広く、たとえば車検をメインに展開している整備業者もあれば、板金塗装、カーナビやETCの取り付けといった電装系の整備など、それぞれの業者によって得意分野は異なります。
現時点では特定のジャンルに特化した整備を行っている業者でも、自動車を保有するユーザーが減少していくと整備のニーズも減り、安定的な経営が成り立たなくなる可能性もあるでしょう。
そこで、より多くの顧客を獲得し安定した売上と収益を確保するために、幅広い分野の整備に対応する動きも見られます。
自社に専門の技術やスキルをもった人材がいない場合、M&Aによって自動車整備会社を吸収合併し事業を拡大していくのもひとつの選択肢となるでしょう。
また、地元で長年にわたって経営してきた自動車整備会社の中には、経営者が高齢化し廃業を選択せざるを得ないケースも増えています。
従業員の雇用を守り、技術を継承していくためにもM&Aは有効な方法ともいえるでしょう。
自動車業界のM&Aの成功事例
大規模な再編が続く自動車業界において、M&Aに成功した企業にはどういった事例があるのでしょうか。自動車部品メーカーと自動車ディーラー、自動車整備会社のケースに分けてご紹介します。
自動車部品メーカーのM&A事例
エンジンや足回り、電装、駆動系に至るまで、幅広い自動車部品の製造を手掛けるSPK株式会社は、トランスミッションの修理サービスやリビルトを手掛ける株式会社デルオートの株式を取得しました。
自動車整備の現場においては、修理にかけるコストをできるだけ安価に抑えるためにリビルト品の需要があります。
信頼性に優れた新品パーツ以外にも、安価でコストパフォーマンスの高いリビルトパーツも取り揃えることで幅広いニーズに対応できることから、SPKにとってメリットの大きいM&Aとなりました。
また、デルオートにとっては事業規模の大きいSPKの傘下に入ることで経営基盤の安定化につながると期待されています。
自動車ディーラーのM&A事例
カー用品の小売大手である株式会社オートバックスセブンは、2021年に株式会社TAインポートの株式を取得し完全子会社化としました。
これはオートバックスセブンが掲げる「5ヵ年ローリングプラン」という経営戦略の中で、「マルチディーラーネットワーク」を構築するための施策として実施されたものです。
TAインポートは栃木県と千葉県でAudi正規ディーラーを運営する自動車ディーラーであり、3つの店舗を展開しています。
自動車ディーラーとカー用品店は関連性が深く、双方のネットワークが構築されることでさまざまな顧客へアプローチが可能となるほか、シナジー効果を活かしたマーケティングの展開によって売上や収益拡大につながると期待されています。
自動車整備会社のM&A事例
自動車ディーラーや販売会社が自動車整備事業をスタートさせるためには、多額の設備投資や専門人材の確保などが不可欠でありハードルが高いものです。
愛知県内で中古車販売を行っている株式会社グッドスピードは、同じく愛知県の自動車整備会社である株式会社ホクトーモータースの株式を取得し子会社化しました。
これにより、販売後の中古車の整備・メンテナンスも自社グループ内で対応でき、アフターフォローの体制を強化することで地域に愛される店舗づくりと企業価値の向上につながると期待されます。
自動車業界のM&Aについてのまとめ
自動車産業は日本の経済を支える基幹産業であり、自動車部品やディーラー、整備といった関連産業も含めると膨大な人が自動車産業に関わっています。
売上規模も大きく安定しているように見える自動車業界ですが、EVや自動運転といった次世代の技術の注目度が高まっていることも事実であり、今後業界再編の大きな波がやってくる可能性は高いといえるでしょう。
激変する自動車業界の中で企業が生き残っていくためにも、M&Aは有効な手段のひとつに挙げられます。
しかし、M&Aを実行するためには専門的な知識やノウハウが必要です。
M&Aによって業界内での生き残りを目指している方は、ぜひM&Aベストパートナーズへご相談ください。
専門的知識とノウハウを持ったアドバイザーが、生き残るための最適な方法をご提案させていただきます。