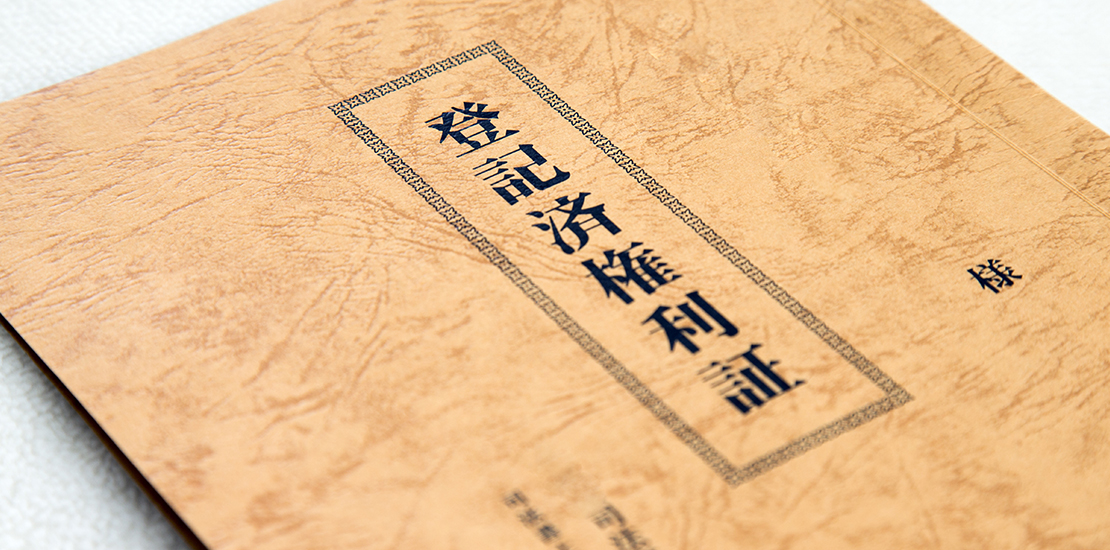PER(株価収益率)は、株式投資をするうえで参考にするべき指標のひとつです。
本記事では、PERの概要、基本的な計算方法から、PBRやROEとの違い、適正な目安、活用する際の注意点まで詳しく解説します。
PERを正しく理解することで、投資判断の精度が向上し、過大・過小評価された銘柄を見極めるヒントを得られます。より正しい投資判断をしたい方や、投資家の視点を学びたい方は、ぜひ参考にしてください。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
PER(株価収益率)とは
PER(株価収益率)とは、「Price Earnings Ratio」の略で、企業の株価がEPS(1株当たり純利益)の何倍かを示す指標です。
この指標を用いることで、その企業の現在の株価が、利益と比較して割高か割安かを判断できるようになります。PERの数値が高いほど割高、低いほど割安と判断されます。
たとえば、成長が期待される企業は、将来の利益増加が見込まれるため、市場の期待が株価に反映され、PERの数字が大きくなる傾向にあります。逆に、成長が鈍化している企業は、利益の伸びが少ないため、PERの数字が小さくなるのです。
PERを活用すれば、投資額の回収にかかる年数を予測することもできるようになります。
PERが20倍の企業は、理論上20年で投資額を回収できる計算になります。
ただし、市場環境や業績変動によって数値も変動するため、PERだけに頼らず、他の指標と組み合わせて分析することが重要です。
計算方式
PER(株価収益率)の計算方法はシンプルで、以下の式を用いて求められます。
- PER = 株価 ÷ EPS(1株当たり純利益)
たとえば、ある企業の株価が1,000円で、EPSが100円の場合、PERは次のように計算されます。
- 1,000円÷100円=10倍
この企業の株価が2,000円に上昇し、EPSが変わらないとした場合は、PERは以下のようになります。
- 2,000円÷100円=20倍
このように、株価が上がればPERも高くなり、逆に株価が下がればPERも低くなります。
また、PERは次の計算式でも求められます。
- PER = 時価総額 ÷ 純利益
ここでいう時価総額とは、「直近の株価 × 発行済の株式数」のことをいいます。
PBRとの違い
PBR(Price Book-value Ratio)は、株価純資産倍率とも呼ばれ、企業の純資産に対して株価がどの程度評価されているかを示す指標です。
計算式は以下になります。
- 株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)
PBRが1倍を下回る場合、その企業の株価は純資産と比べて割安と判断されることが一般的です。
PER(株価収益率)とPBR(株価純資産倍率)は、どちらも企業の株価が適正かどうかを評価する指標ですが、算出方法や着目点に違いがあります。
PERが企業の「収益力」を評価するのに対し、PBRは「資産価値」に焦点を当てる点が大きな違いです。
また、PBRは企業の一時点の純資産を基準にするため、収益が不安定な企業で一定期間ごとに計算すると、その都度変わってしまう可能性は高くなります。
そのため、PERとあわせて分析することが重要です。
ROEとの違い
ROE(Return On Equity)は、自己資本利益率とも呼ばれ、企業が株主から調達した自己資本を活用して、どれだけの利益を上げたかの収益効率を示す指標です。株主にとっては投資の回収率の指標にもなります。
計算式は、以下になります。
- 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)
この計算式で算出された数値が高いほど、資本を効率的に活用していると評価されます。
PER(株価収益率)とROE(自己資本利益率)は、どちらも企業の収益性を評価する指標ですが、それぞれの異なる部分に焦点を当てています。
どちらも当期純利益を基準に評価されますが、ROEは企業の収益効率を、PERは市場での評価を示す点が大きな違いです。
PERの目安
PERの数値は絶対的な基準ではなく、業種や企業の成長段階、市場環境によって変動するため注意が必要です。
成長が期待される企業や先進市場の銘柄は、将来の利益増加が見込まれるためPERが高くなりやすく、成熟企業や安定した業種ではPERが低めになる傾向があります。同じPERの企業でも、業績の安定性や成長によって評価が異なります。
一例として、PER20倍の企業があった場合、一方は急成長中のIT企業で、もう一方は成熟した製造業であるとします。前者は将来の利益拡大が期待されるため、PER20倍でも割安と見られる場合がありますが、後者では割高と判断するのが妥当といえるでしょう。
PERを判断する際は、同業種の平均値や市場全体の動向を参考にすることが重要です。
さらに、PBRやROEなど他の指標と組み合わせることで、より正確な企業評価が可能になります。
単独の数値だけでなく、総合的に見て判断することが大切です。
PERが高いのと低いのではどちらがいい?
PER(株価収益率)の高低は、単純にどちらが良いとは言い切れません。
それぞれにメリットとデメリットがあり、企業の成長性や市場環境によって判断する必要があります。
PERが低い企業は、一般的に株価が割安と判断されます。
その企業の将来の成長性に対する株式市場の期待が低いということになり、今後も株価が上がる可能性は低いといえるでしょう。したがって、中長期的な投資には向いていません。
具体的な例として、日本経済新聞が公開した2025年2月28日の日本株ランキングでは、東京電力ホールディングス、北陸電力、北海道電力などのインフラを提供する企業が低PER銘柄として挙げられています。
しかし、成長が見込まれるにもかかわらず、市場の株価にその期待が反映されていないことがあるため、そういった企業の場合は、買い時といえるでしょう。
一方、PERが高い企業は、将来の成長期待が大きいことを意味します。
とくにITやバイオテクノロジーなどの成長分野では、利益がまだ少なくても、将来的な拡大を期待されPERが高くなることがあります。
PERを活用する際のポイント・注意点
PERは有用ですが、活用時のポイントや注意点も多くあります。
PERだけで判断しない
前述の内容にもある通り、投資判断をする際に、PERだけに頼るのは危険です。
企業の成長性や状況をより正確に把握するためには、PBR(株価純資産倍率)やROE(自己資本利益率)などの他の指標もあわせて確認することが重要です。
また、企業の利益を評価する際には、営業利益の数値だけでなく、どの会計基準を採用しているかも確認する必要があります。
たとえば、日本基準(J-GAAP)と国際会計基準(IFRS)では利益の計算方法が異なるため、同じPERでも実際の収益性が大きく異なる場合があります。
海外の会計基準を採用する企業の収益性を判断する際は、営業キャッシュフローを活用するとよいでしょう。
マイナスが出る場合もある
企業の純利益がマイナスになると、PERもマイナスになります。
この場合、通常のPERのように「数値が低いほど割安」とは判断できません。
PERがマイナスになる代表的なケースとして、以下のような状況が挙げられます。
- 一時的な業績悪化による赤字が出たとき
- 事業再構築や大規模な投資による一時的な損失が出たとき
- 経営不振や市場環境の悪化による継続的な赤字となったとき
前者2つのような一時的な赤字であれば、事業の成長過程における投資の影響であり、将来的な利益回復が見込める可能性は高いです。
そのため、PERがマイナスであっても、必ずしもネガティブな要因とは限りません。
しかし、後者のような長期間にわたり赤字が続く企業では、根本的な経営の問題があるため、慎重な投資判断が求められるでしょう。
比較は同業種間や同一企業の過去の傾向で行う
業種によって平均的なPER水準は大きく異なります。
同じPER20倍でも、業界が異なれば割安・割高の基準も変わるため、業種ごとの平均PERを把握することが大切です。
そのため、単純に数値だけを見て判断するのではなく、同業種の企業と比較するようにしましょう。
株価を決める要素には、投資家の期待も含まれます。
だからこそ、成長が期待されるITや医薬品業界などの企業は、将来の利益拡大が見込まれるため、PERが高くなる傾向があるのです。
そして、食品などの景気変動の影響を受けない生活必需品を取りあつかうような企業も、投資家から期待され高い傾向にあります。
過去の数値も確認する
PERが上がったり下がったりしたとき、その要因は一時的なものである場合があります。
そのため、過去のPERの推移を確認し、長期的な視点で判断することも重要です。
たとえば、新規事業への参入や大規模な設備投資を行った場合、一時的に利益が減少しPERが大きく下がることがあります。
このようなケースでは、事業の成長が進めば利益が回復し、PERも正常な水準に戻る可能性が高いです。
逆に、一時的な利益の急増によってPERが異常に低く見える場合もあり、実際の収益力を見誤ってしまうかもしれません。
PERがマイナスになった場合も、その原因を特定する手段のひとつとして、過去の数値を確認することが大切です。
単なる一時的な業績悪化なのか、それとも事業の根本的な問題なのか、変動の理由を分析し把握したうえで投資判断を行うようにしましょう。
業種として高い・低いがある
前述の内容でも触れたように、PERには、業種によって高くなりやすいものと低くなりやすいものがあります。
これは、PERの算定に使われる株価が、投資家が抱く将来の成長期待が反映されるものであるためです。
だからこそ、成長が期待される業種ではPERが高く、安定した業種では低くなる傾向があります。
ただ、どの業種であっても、独自のサービスや技術によって売上を伸ばしている企業は、市場の期待が高まり、PERが上昇する傾向にあります。
まとめ
PER(株価収益率)は、その企業の現在の株価が、利益と比較して割高か割安かを判断できるようにする指標です。
計算方法はシンプルでわかりやすいですが、出る数値は一時的な業績変動や会計基準の違いなどで変わり、その適正水準は業種や市場環境などに左右されます。
そのため、PERの数値だけで投資判断をしてはいけません。
判断の際には、PBRやROE、同業他社との比較や過去のPER推移などとあわせて分析することが重要です。
M&Aベストパートナーズでは、こうした多角的な視点が必要な分析にお悩みの方に、経験豊富な専門家から、最適なサポートを提供します。
自社の正確な企業価値を把握できずにお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。