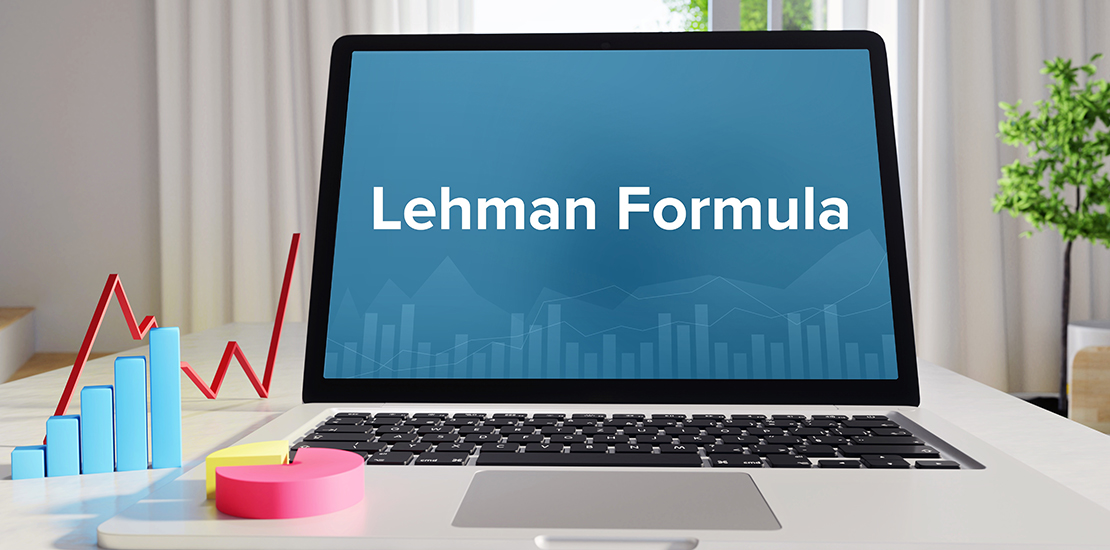企業経営において、資金調達は欠かせません。その際、金融機関が求める「個人保証」は重要な役割を果たします。
そのメリットとしては、企業に対する信頼の向上や融資の受けやすさが挙げられる一方で、事業撤退の難しさや個人資産を失ってしまうリスクといったデメリットも存在するため注意が必要です。
本記事では、個人保証の基本概念やメリット・デメリットを詳しく解説し、関連するガイドラインについても紹介します。
個人保証に対する理解を深め、経営判断に役立つ知識を得たいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
↓ こちらから知りたい情報へ移動できます ↓
目次
個人保証とは
個人保証とは、企業が金融機関から融資を受ける際、経営者や第三者が債務の返済を保証する制度のことを指します。
民法第446条では「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」と規定されており、金融機関が企業に対して融資を行う際に、確実に債務が回収できるよう、個人保証を求めることが一般的です。
保証には大きく分けて「人的担保」と「物的担保」の二種類があります。
人的担保は、保証人が債務を引き受けることで信用を補完する仕組みであり、個人保証はこの範疇に含まれるものです。一方、物的担保は不動産や預金などの資産を担保にする形態となります。
そして個人保証には、「単純保証」と「連帯保証」の二種類が存在します。
単純保証は、主たる債務者が返済不能になった場合に初めて保証人が責任を負う形式です。
一方、連帯保証では、主たる債務者と保証人が同等の責任を負うため、金融機関は債務者が返済可能かどうかに関わらず、保証人に直接請求できます。このため、連帯保証は保証人にとっては負担が大きく、リスクが高い仕組みといえるでしょう。
個人保証の目的は、企業への信頼を補完し、金融機関が融資を実行しやすくすることにあります。
とくに中小企業では、財務基盤が弱いため、経営者自身が個人保証を提供することで資金調達を円滑に進めることができるようになるのです。
しかし、個人保証は経営者個人の財産に影響をおよぼすものであるため、慎重に検討する必要があります。
個人保証のメリット
個人保証の主なメリットとして、以下の3つが挙げられます。
会社の信用(与信力)が高まる
中小企業は一般的に、他者からの信用が不足しがちです。これは、財務基盤が脆弱であることや、長期的な実績が少ないことが原因となります。
とくに設立間もない企業は、決算書の履歴が短く、金融機関や取引先からの信用を得るのが難しい傾向にあるのです。
だからこそ、融資を受ける際に金融機関はリスクを考慮し、保証や担保を求めることが多くなります。
大企業は投資家からの信頼を担保する必要がありますが、株式市場を通じて資金調達を行うことができます。しかし、中小企業にはその選択肢がありません。金融機関からの融資が資金調達の中心となるため、個人保証が重要な役割を果たすようになるのです。
もともと信用があったとしても、経営成績が悪化すれば、個人保証なしでは資金調達が困難になる場合が多いです。しかし、そうした企業であっても、経営者が個人保証を提供することで、企業への信用が向上し、必要な資金を調達しやすくなります。
IR情報の信頼性が高まる
中小企業のIR(投資家向け広報)情報は、大企業と比べて信用されにくい傾向にあります。
これは、中小企業だと十分な会計監査が行われていないことが多く、財務情報の透明性や正確性が確保されにくいことが主な原因です。
それでも、資本市場からの直接的な資金調達が難しい中小企業では、金融機関や投資家に対する情報の信頼性が重要な要素となります。
こうした状況において、個人保証はIR情報の不確かさを補完する役割も果たします。経営者自身が個人保証を提供することで、金融機関や投資家は「経営者が企業の責任を負う意思がある」と判断し、企業への信用が高まるのです。これにより、財務情報に対する不信感を補わせることができるというわけです。
融資を受けやすくなる
個人保証をつけることで、経営者個人への信用が加わり、企業の信用度が高まります。
とくに中小企業の場合、財務基盤が脆弱なことが多く、法人単体では信用が不足しがちです。そして金融機関は貸し倒れなどのリスクを可能な限り避けたいと考えています。
そこで個人保証によって経営者自身がそうしたリスクを下げることで、融資の承認を得やすくできるのです。
また、多くの中小企業で、法人と個人の資産が明確に分けられていないケースがみられます。そのため、金融機関の審査は厳しくなり、十分な信用を得るのが難しくなることがあるのです。しかし、個人保証を行えば、経営者の個人資産も考慮されるため、融資の承認が下りやすくなります。
個人保証のデメリット
ここまで、個人保証のメリットをみてきましたが、デメリットがあることにも注意しなければいけません。
経営悪化の際に個人に大きな悪影響がある
個人保証を行う最大のリスクに、経営悪化時には経営者個人が大きな負担を負う可能性があるという点が挙げられます。
経営が悪化してしまうと、預貯金など私的な財産を切り崩さなければならないケースが多く、生活していくことすら危うい状況に追い込まれてしまうかもしれません。せめて生活費を守ろうとしたとしても、金融機関は債権回収を優先するため、個人資産の差し押さえが行われる可能性は高いです。
そのため、過重な負担が原因で、経営者の生活が破綻してしまう例は少なくありません。家族がいれば、当然その人たちの生活にも影響します。
そうした事態に陥ったときはもちろん、そうなるリスクがあるというだけで、精神的な負荷が大きくなることについても考慮する必要があるでしょう。
事業の撤退が簡単にできない
個人保証をしている場合、経営が悪化しても簡単に事業を撤退する判断ができなくなってしまいます。会社の債務を個人で保証しているため、事業を畳んだとしても、債務の返済義務だけが残り、経営者の個人資産にも大きな影響をおよぼすからです。そのため、撤退を決断する際には、より慎重な判断が求められるようになります。
そのため、採算性の低い事業を続けざるを得ないケースもあります。保証人としての責任を果たすため、わずかな利益しかない事業を無理に継続しなければならないことがあるのです。その結果、状況がさらに悪化してしまう可能性もあります。
ただし、株式会社は有限責任、つまり会社が倒産した際、出資者が出資した金額を超えて責任を負うことはないようになっています。そのため、経営が困難になり、挽回の見込みが完全になくなったのであれば、会社を清算して新たな事業に挑戦するという手段も有効でしょう。
事業承継や起業が難航する
個人保証は、事業承継や起業の際に大きな障害となることがあります。
とくに、事業承継においては、経営権だけでなく個人保証も後継者が引き継がなければならないため、後継者候補が個人保証のリスクを負うことに難色を示すことが多いのです。
親族内での承継や社内で後継者を選定する場合でも、個人保証が原因で後継者が見つからない事態に陥ることが多くあります。
また、起業時には、ほとんどの場合、個人保証を求められるため、起業したい人は、前述のリスクを理由に新規事業の立ち上げを断念することもあります。
経営者保証に関するガイドラインについて
「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業経営者の個人保証に関する負担を軽減し、事業の継続性を高めるために策定された指針です。
2014年2月に制定され、企業が融資を受ける際の過剰な個人保証を見直すための基準として活用されています。
従来、企業が金融機関から融資を受ける際、経営者が連帯保証を求められるのは一般的でした。たとえ信用の高い企業であっても、個人保証を外すことは極めて難しく、事業の撤退や承継を妨げる要因となっていました。しかし、こうした過剰な担保の必要性に疑問が投げかけられるようになり、経営者の負担軽減を目的として、金融機関と中小企業団体の共通基準としてガイドラインが策定されたのです。
このガイドラインの適用によって、以下の条件を満たせば個人保証の解除が可能になりました。
- 企業と経営者の資産・経理が明確に分離されていること
- 財務状況が健全であり、企業の収益力が十分であること
- 適切な情報開示を行い、金融機関との信頼関係を維持していること
また、このガイドラインを活用することで、経営者には以下のようなメリットもあります。
- 信用情報機関に登録されず、次の事業に影響を与えない
- 万一の場合でも最低限の財産を確保できる
- 事業承継がスムーズに進められる
これらのメリットにより、経営者のさまざまなリスクを大幅に軽減することができるのです。
このように、経営者保証に関するガイドラインは、中小企業の成長と経営の自由度を高める重要な制度として機能しています。
ガイドラインの注意点
「経営者保証に関するガイドライン」は、個人保証の負担軽減を目的とした指針ですが、注意すべきは、このガイドラインに法的拘束力がないということです。
つまり、これはあくまで、自発的に遵守されることが期待されるものになります。
そのため、金融機関によって対応が異なり、すべての融資が無担保・無保証で行われるわけではありません。
条件を満たしていても、個人保証を解除できるわけではないことにも注意が必要です。
ただ、ガイドライン策定後も、2020年の民法改正、廃業時における経営者保証に関するガイドラインの基本的な考え方の改定、経営者保証改革プログラムの策定など、個人保証をなるべく行わないで融資を得られるよう、少しずつ改正されてきています。
とくに経営者保証改革プログラムは、個人保証に頼らない融資慣行を確立することを目的としたプログラムで、金融庁が経済産業省や財務省と連携して策定されたものです。そのため、各省庁が個人保証の問題に注目しているとも言えるでしょう。
まとめ
個人保証は、企業が金融機関から融資を受ける際に経営者や第三者が債務の返済を保証する制度です。
これにより企業への信用が高まり、融資を受けやすくなるメリットがある一方、経営悪化時には個人資産に影響してきたり、事業承継が困難になったりといったデメリットも存在します。
しかし、法的拘束力はないものの経営者保証に関するガイドラインが策定されていたりもするため、可能な限り個人保証を避けられるよう交渉するといいでしょう。
M&Aベストパートナーズでは、経営者の負担を軽減し、スムーズな事業承継を支援するサービスを提供しています。個人保証が原因で事業承継にお悩みの方は、ぜひご相談ください。